活動記録
ACT

第227回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年12月7日)
| 第227回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年12月7日) 報告内容 『ジャン・クリストフ』 第四巻 反抗 Ⅰ「ぐらつく砂地」(後半) 発表者 清原 章夫 さん 1.あらすじ クリストフの演奏会は失敗に終わった。作品は、未熟でその場で理解されるには新奇すぎた。そして、聴衆はこの無礼な青年をこらしめることに、喜びを感じていたからだ。それまで彼の音楽に興味を持っていたように見えた人々も、彼に激励の言葉一つかけなかった。彼らの中でも誠実な人々は、彼の初期の愚劣な作品を愛したが、新作は愛することができなかった。 だが、失敗を認められない彼は、現在の自分を理解してもらうため、自分を弁明し、議論しようと欲した。そんな時、フランツ・マンハイムというユダヤ人銀行家の息子と知り合った。彼はクリストフに、自分達が作っている雑誌『ディオニゾス』に音楽評論を書いて欲しいと依頼した。クリストフは、最初当惑したが、なんでも言っていい権利を与えてもらうという条件で承諾した。 ある晩、マンハイムは、クリストフを晩餐に家へ連れてきた。クリストフは、はじめてユダヤ人の家に入った。彼の住む小都市でも、ユダヤ人に対する偏見と、素朴ではあるが不当な、ひそかな敵意があった。クリストフはこうした偏見を全然もっていなかった。自分の周囲に対する反抗心によって、むしろこの異民族に心を引かれていたが、この民族のことはほとんど知らなかった。 クリストフは、家に入った瞬間からフランツの妹のユーディット・マンハイムばかり見ていた。彼女は、美しく知性があり、望めばどんな学問にも成功するだけの頭脳を持っていた。彼女は、彼にピアノを弾かせた。彼女は音楽を好きではなかったが、理解はできた。そして、彼の音楽を聴いて、感動はしなかったが、彼の音楽が独創的なものであることは認めた。彼は、その晩は彼女としか話さなかった。しかし、彼はユーディットが思うほど、彼女に心を奪われてはいなかった。それは、アーダとの恋愛からまだ日が浅かったからだ。 しばらくして、ユーディットはクリストフが、ドイツ芸術とドイツ精神との偏見に対して、強硬な攻撃をしかけようと決心して、もしそれをどこまでも執拗につづけると、すべての人々を、また保護者までも敵にまわすようなことになるであろうと見抜いた。また、彼の目的は成功ではなく、自分の信念であること、そして彼は芸術を信じ、自分の芸術を信じ、自分を信じていることを知ると、もはや彼に興味を持たなくなった。クリストフも彼女の、利己心を、冷酷さを、性格の凡庸さを見た。また、彼ははじめ、他民族から独立しているこの力強いユダヤ人の中に、自分の戦いの同盟者を見いだせるものと期待していた。しかし、この民族は、世に言われているよりずっと弱いものであり、外部の影響に左右されやすいものと、彼は直感でそう思いこんだ。クリストフが自分の芸術のてこを置く支点を見いだしうるのは、まだここではなかった。彼はむしろ、この民族とともに、砂漠の砂に飲みこまれかかったのである。彼はこの危険をさとったので、また、その危険をおかすだけの自信が感じられなかったので、マンハイム家に行くのをぴたりとやめた。 雑誌は、最初のうちは万事調子よくいった。最初の評論の題は、『音楽の過剰』というものだった。 「音楽が多すぎる!諸君は自分を殺し、音楽を殺している。諸君が自分を殺すことは、これは諸君の勝手である。だが、音楽を殺すことは、これはやめてもらいたい!聖なる調和と低劣なものを同じ籠の中に投げこみ、たとえば諸君がいつもやっているように、『連隊の娘』による幻想曲とサキソフォーン四重奏との間に『パルシファル』の前奏曲を入れたり、あるいは黒人舞踏(ケーク・ウォーク)の一節とレオンカヴァルロの猥雑な曲をベートーヴェンのアダジオの両側においたりして、世にある美しいものを汚すのはゆるせない。諸君は音楽的な大国民だと自慢している。諸君は音楽を愛していると自負している。だが、どんな音楽を愛しているのだ?良い音楽をか?それともくだらない音楽をか?諸君はそのいずれにも等しく拍手を送っている。さあ、いよいよ、選択したまえ!本当になにを欲しているのだ?諸君はそれを知らない。知ろうと欲していない。諸君は決心することを、危険をおかすことをあまりにも恐れている…そんな用心など悪魔にくれてしまうがいい! ― 自分たちは流派を超越している、というのか? ― 超越しているとは、その下にあるということだ…」 こうした血気にはやった、過激な、そしてかなり悪趣味な大言壮語に、もちろん非難の叫びがあがった。だが、みなが対象にされていながらも、だれもはっきりそれとさされているわけではないので、だれも自分のことだと思う者はなかった。しかし、次の評論では、みなが槍玉にあがった。 真っ先にやられたのは指揮者たちだった。自分の町や、近隣の町の同僚の名前をちゃんとあげ、あるいは、名前をあげない場合には、だれとはっきりわかるようなほのめかし方をした。過去の偉大な芸術家たちを《古典的な人々》として解釈している国立音楽学校の大物たちに対しては、皮肉を浴びせた。名人芸の演奏家の機械的な演奏は、技芸専門学校の領分であるとして、批判すらしなかった。 次は歌手の番だった。彼らの洗練されない鈍重さと、田舎くさい誇張とについては、クリストフには言うべきことが胸につかえていた。特にメロディーの美しさが本質的である、古典的作品における歌のまずいことであった。人々は、詩を歌っていた。人々は、細部の閑却や、醜さや、音の間違いさえも大目に見ていた。作品の全体だけが、思想だけが大事であるという口実の下に。 「思想!それについて話してみよう。まるで諸君は思想を理解しているような顔をしている。…だが、思想を理解していようといまいと、どうぞ、思想が選んだ形式を尊敬していただきたい。なによりもまず、音楽は音楽でなければならない。いつまでも音楽のままでなければならない。」 彼は、芸術家たちを非難するだけでは満足しなかった。彼は舞台からおりて大口あけて演奏を聞いている聴衆をなぐりつけた。拙劣な作品に拍手するのを非難するだけでなく、立派な作品に拍手を送ることをもっとも非難した。例えば、ベートーヴェンの『荘厳ミサ』のあとではそれはとんでもないことだと。 彼は、批評界にも飛びこんだ。彼が子供のころ紹介された作曲家のハスラーに対して、秩序と原則に戻るように言っている愚かしい批評家を攻撃した。 「秩序だと!秩序だと!諸君は警察の秩序しか知らないのだ。天才は踏みかためられた道は歩かない。天才は秩序を創造し、自分の意志を法則にまでする。」 こうした、傲慢な宣言ののち、クリストフはこの運の悪い批評家をつかまえて、彼が近ごろ書いた愚劣な論説を全部取り上げて、まるで教師が生徒に対するようにいちいち訂正した。全批評界は侮辱を感じた。彼らは、毎日の新聞に、不実で、皮肉で、侮辱的な短文を繰り返し載せた。いつも名ざしはしないが、はっきりそれとわかるように、横柄なクリストフを冷やかしていた。 やがて人々は、彼の評論をこれからも載せるのであれば、他の編集者たちもクリストフ同様に非難せざるをえないとほのめかした。編集者たちはクリストフに、批評の調子をやわらげさせようとしたが、彼は全然調子を変えなかった。 マンハイムは、クリストフの主張と、この地方でもっとも進歩的なワグナー協会を結びつけたほうが有利だと思いつき、クリストフをワグナー協会に入会させた。しかし、そこは一つの音楽学校と同じように狭苦しく、また芸術会の新参者であっただけに、いっそう偏狭だった。クリストフは、マンハイムにワグナー協会から脱会すると叫んだ。マンハイムは、クリストフの作品を演奏するには、仲間や友人が必要で、それらが無くては、やがて誰も彼の作品を演奏しなくなるだろうと言った。クリストフは、それに答えて言った。 「それでも結構だ!じゃきみは、ぼくが有名な人間になりたがっているとでも思っているのかね?…なるほど、ぼくはそうした目的に向かって全力をつくしていた…意味のないことだ!ばかげたことだ!くだらないことだ!…まるで、いちばん卑俗な自尊心の満足が、光栄の代価であるあらゆる種類の犠牲―たとえば、倦怠、苦痛、恥辱、堕落、恥ずべき譲歩などの償いででもあるかのようにね!もし、今でもそうした心配ごとにぼくが頭を悩ましているとすれば、悪魔にさらわれるがいい!もうそんなことはないんだ!聴衆とか有名とかいうことには、もうかかわりたくない。有名なんて、卑しいくだらないことだ。ぼくは一人の私人でありたい。自分のために、自分が愛している人々のために生きたい…」 その間にも、クリストフは雑誌『ディオニゾス』で、激しいたたかいをつづけていた。彼はもう批評の仕事にはうんざりしてやめたいと思ったが、彼を沈黙させようと努力している人々に降参したように見られるのがいやで、つづけていた。 マンハイムは、クリストフを黙らせるかわりに、クリストフが、自分の書いたものを決して読み返さないことを利用した。マンハイムは、クリストフの原稿を校正する際、正反対のことを言わせるように改作した。クリストフから嘲られどおしだったある音楽家たちは、彼がだんだんおとなしくなって、しまいにはほめてくれるようにさえなったことを見てびっくりした。クリストフの周囲では、人々の顔が明るくなり、彼のきらっている人たちが、道で挨拶するようになった。 2.ロランのユダヤ人観 クリストフが最初に知り合ったユダヤ人が、フランツ・マンハイムとユーディット・マンハイムだった。ロランもクリストフと同様に、ユダヤ人に対して偏見はなかった。彼には、エコール・ノルマル(高等師範学校)で知り合った、アンドレ・シュアレス(詩人・批評家)や作家のシュテファン・ツヴァイクのようなユダヤ人の親友もあったし、ドレーフュス事件のようにユダヤ人がいわれのない不正や憎悪の犠牲となったときには、常にその味方になっていた。また、彼の最初の妻クロティルドもユダヤ人であった。しかし、クリストフが言っているように、ユダヤ人が確とした信念をもっていないこと等、ユダヤ人の欠点も認識していた。 3.ロランの音楽評論 クリストフが発表した評論は、実際にロランが書いた評論や、日記、手紙を読むとロラン自身の考えや意見であることがわかる。また、新村猛氏によると、ここでのドイツ批判は、ゲーテやニーチェの自国に対する批判に負うところが大きかったそうである。(『ロマン・ロラン』新村猛著・岩波新書) ロランは、日記に演奏会の感想を多く残している。例えば、 「同じ演奏会で、パデレフスキーとかいう人が演奏。二十五歳から三十歳ぐらいで、背が高く、やせていて、頬がへこみ、理髪屋の店員のように髪をもじゃもじゃとさせ、その髪がブロンドで色が薄くてちぢれている。リストの『ラプソディー第十二番』をみごとに弾く。しかしベートーヴェンの『変ホ長調協奏曲』[皇帝]は、まったくぼくをいら立たせた。途中で時どきしゃっくりをする演奏。信念もなく、深い感情もない。この強く、はげしく、英雄的な音楽を、こっけいなほどだらけさせている。もうクラシック[ロマン派以前の作品]など演奏しないがよい。あまりにもポーランド的すぎる。」(『ユルム街の僧院』「一八八九年三月十日の日記より」蛯原徳夫・波多野茂弥訳 みすず書房) また、友人達へ出した手紙の中でも、演奏会の感想を書いている。これらの、公表することを目的としない文章には、ロランの率直な意見が述べられていて大変興味深い。 「先日のバッハとヘンデルの音楽会はかなりきれいでした。―隣に二人のドイツ人の夫婦がいましたが、私はおもしろくおもいました。ヘンデルが演奏されています。彼らは平然としています。バッハが演奏されます。依然たるものです。欠伸をはじめます。スカルラッティをやります。彼らはなかば眼ざめます。もう少しのところで、彼らはその曲を口笛でやりかねないところでした。ギルマン(オルガン奏者)の曲になります。おや!こんどは拍手をおくります。B・ゴダール(グノーのいちばんくだらない弟子の一人)の感傷的で味気ない作品になると、彼らの感激は無際限になります。彼らはほんとうに幸福です。―これがワーグナーのドイツです!」(『マルヴィーダ・フォン・マイゼンブークへの手紙』「一八九二年四月三十日土曜日より」宮本正清・山上千枝子訳 みすず書房) 公表された評論では、クリストフの発言を連想させられるものが多い。 「最後に、ドイツで音楽を脅かしている最大の危険について述べたい。―ドイツには音楽が多すぎる。―これは逆説ではない。私は芸術にとっては芸術の度外れた過多ほど不幸なものが他にあろうとは思わない。音楽が音楽家を弱らせる。音楽祭につぐ音楽祭、これらのストラスブウルの祭りの翌日アイゼナハでバッハ祭がはじまった。それからその週末にはボンでベエトオヴェン祭。音楽会、劇場、合唱団、室内楽団が音楽家の全生活をのみこんでしまう。いつかれはひとりでいる時間、自分の内面の音楽を聴く時間があるのだ?このような慎みのない音楽奔流が魂の最後の隠れ家にまではいりこみ、その力をうすめ、その聖なる孤独とひそかなるその思想の宝を破壊する。」(『今日の音楽家たち』「フランス音楽とドイツ音楽」一九〇五年 野田良之訳) 4.ロランの受けた音楽教育 『ジャン・クリストフ』を読むと、ロランがどれだけ音楽を愛し、音楽と一体になっていたかがわかる。しかし、彼がエコール・ノルマルで学んだのは、歴史学であった。彼は、音楽をどのようにして学んだのだろうか。 最初の先生は、母であった。妹といっしょにピアノの手ほどきを受けた後、クラムシーに住み着いたポルタという亡命イタリア人について、やはり妹といっしょにピアノを学んだ。パリに引っ越してからは、母が娘時代に習っていたジョゼフィーヌ・マルタンに学んだ。彼女はモーツァルトの演奏が得意であった。これが、ロランが受けた技術的な教育だった。それに、加えて演奏会による教育があった。毎日曜の夕方彼は、音楽会を聴きにいった。パドゥール、コロンヌ、ラムールが指揮する管弦楽、ピアノではアントン・ルビンシュタインの獅子の爪、プーニョのびろうどのように柔らかい手、ディエメルの水晶のように澄んだ演奏、バイオリンではヨアヒムやイザイやサラサーテの魔法の弓によって、モーツァルト、ベートーヴェン、シューマン、ベルリオーズ、ワグナーの芸術に浸った。 そして、一八八八年の夏休みにスイスで出会った、ショパンの師匠フェルディナント・ヒラーの孫弟子の老侯爵ド・ブルイユポンによってベートーヴェンの扉を開く鍵を与えられた。ロランは、彼に自分の音楽への認識を高めるために忠言を求めた。 「パリではほんとうにあなたのためになる先生はみつからないでしょう。―しかし何よりもまず、オーケストラでベートーヴェンの交響曲を聴きなさい!(それは彼の言葉を待つまでもなかった!)あなた自身で自分の教育をしなさい!一つか、二つか、また三つの作品に専心しなさい。それを掘り下げなさい、その作品にふくまれているすべてのものを発見しなさい、それらの作品を理解しなさい、それらをめとりなさい!交響曲の音楽会から帰ったら、音色の効果をピアノで再現しなさい、音の出し方やヴィヴラートを長く研究しなさい。あなたのメカニズムですが、それはすでに見事です、それを自分で磨きなさい、しかし極端にならないように!」(『回想記』宮本正清訳 みすず書房) ロランのピアノ演奏はかなり高い水準に達していた。また、作曲もしていたが、楽譜を公けにしなかった。あるレコード会社から、未発表のピアノ・ソナタの自作自演による録音を求められたが、固く断ったそうである。 |
第225回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年10月26日)
| 第225回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年10月26日) 報告内容 『ジャン・クリストフ』 第四巻 反抗 Ⅰ「ぐらつく砂地」(前半) 発表者 清原 章夫 さん 1.あらすじ ゴットフリートによって危機を脱したクリストフは、一年来彼を束縛していた恋の情熱から脱却して自由になり、幸福を感じていた。 彼は再び作曲の仕事をはじめた。楽想は汲み尽くせないほどあふれてきた。彼は自分の力を自覚したと同時に、それまで、尊敬していたあらゆるものを、初めて直視した。 彼は市立音楽堂の音楽会へ行った。プログラムはベートーヴェン『エグモント序曲』ヴァルトトイフェルのワルツ、ワグナー『タンホイザー』の中から『ローマへの巡礼』、ニコライ『陽気な女房たち』『アタリー』のなかからの『宗教的なマーチ』『北極星』による一幻想曲、シューマンとブラームスの歌曲だった。これらの曲の演奏を聴いているうちに、クリストフはだんだんあきれてきた。そして突然、万事が嘘だと思われだした。彼がもっとも愛していた『エグモント序曲』までがである。それは、演奏家や聴衆のせいでなく、作品そのものの中に、ドイツ思想が水のそこでまどろんでいるのを見た。 彼は家に帰り、「神聖視されている」音楽家たちの作品をあらためて読み直した。そして彼がいちばん愛していた巨匠たちの中のある人々が嘘をついているのに気づき驚いた。ドイツ国民の芸術的至宝とされるものの中に、おびただしい凡庸さと虚偽が見出され彼は唖然とした。吟味に耐えたものは、ほんのわずかだった。最愛の作品の中にこれらの欠点を見た時、最愛の友を失ったかのような気持ちになり、彼は泣いた。 例えば、メンデルスゾーンには、ゆたかで空虚な憂鬱、お上品な幻想、分別たっぷりの虚無があった。ヴェーバーは、彼の心情の乾燥と、たんに頭脳だけの感動があった。リストはサーカスの馬術師であり市場の大道商人だった。シューベルトは、自分の敏感さにおぼれているかのようだった。偉大なバッハでさえ、虚偽と、流行かぶれのつまらない点があり、ベートーヴェンあるいはヘンデルのような人々の作品のなかに吹きわたっている強壮な外気が彼の音楽にはなかった。そして、クリストフは古典の作曲家たちの作品において、自由が欠けていることが不満であった。 だからといって、彼が浪漫派の人々にはいっそう寛大だというわけではぜんぜんなかった。奇妙なことに、彼をもっともいらだたせたのは、例えばシューマンのように、もっとも自由でありもっとも自発的であり、たんなる組み立て師であることがもっとも少ないと自称した人々であった。シューマンの実例からクリストフが理解したドイツ音楽の最悪の虚偽は、ドイツの音楽家たちが少しも実感していない感情を表現しようとするときにではなく、彼らが実際に感じた諸感情を表現しようと望んだ時に、むしろはるかに多くあらわれるのだ。ドイツの音楽家が素朴で信頼心に充ちていればいるほど、ますますドイツ魂の弱点、その不確かな基礎、そのふわふわした感じかた、独立的率直さの欠如、やや陰険な理想精神、自分自身を直視することの無能力を示すことになる。 さらに、クリストフはワグナーの作品を読みなおしてみて、歯ぎしりをした。『ニーベルンゲンの指輪』の「四部作」には、あらゆる種類の嘘―嘘の理想主義、嘘のキリスト精神、嘘のゴチック精神、嘘の伝説、嘘の神性、嘘の人間性がつまっていた。あらゆる因習をくつがえそうと気負っていたこの作品ぐらい大きな因習が誇示されているものはなかった。 だが、誰がクリストフ以上に、彼らを愛しただろうか。シューベルトの善意を、ハイドンの無垢を、モーツァルトの愛情深さ、ベートーヴェンの英雄的な偉大な心を感じた者があったであろうか。ヴェーバーの森のそよぎの中に、またバッハの音楽のかずかずの大伽藍、その大きな影の中に、彼以上に敬虔な気持ちで魂を潜めた人間があったろうか。 しかし、クリストフは彼らの嘘に苦しみ悩んだ。かつて夢中になって彼らを信じたことについて、自分自身を、また彼らを恨んでいた。そしてそれはいいことだった。子供は教育や周囲で見聞きすることによって人生の本質的な真実にまじっている実に多くの嘘と愚かしさとを吸い込むので、健全な人間になろうと望む青年がまず第一にしなければならぬことは、すべてを吐出すことである。 それ以降、クリストフは自分の感情を隠すようなことはしなかった。会う人ごとや、演奏会の真最中に作品や人物に対して途方もないことを言っては人々を怒らせた。彼を恨む人々は、彼の父方がフランドル地方の出である、純粋なドイツ人でないことを思い出し、この他国からの移住者が、国家的栄光に難癖をつけることは、別に意外なことではないと思った。 クリストフは、自分の作品を音楽会で発表することにした。練習の際、オーケストラの団員は自分たちが演奏している作品についてまるきり理解していなかった。また、彼らはこの新音楽の奇抜さに狼狽させられていたが、自分の意見を作りあげる暇と能力がなかった。クリストフの自信は、団員たちを威圧していたし、彼らは従順でよく訓練されていたので練習は問題なかった。 しかし、歌曲を歌う女性の独唱者だけは、自分のやり方をとおした。クリストフは、彼女の劇的な力をもう少し抑制して歌うようにたのんだが、したがわなかった。ついにクリストフは、歌曲はプログラムから引っ込めてしまうと言ったため、最後の練習の際、彼女はおとなしく彼の言うとおりに歌った。 演奏会の当日になった。大公が来られなかった。また聴衆も、クリストフが子供のころの音楽会は満員だったのに、会場の三分の一は空だった。クリストフはまだ十七才だったが、聴衆は半ズボンの子供のほうが興味があったからだ。 序曲がはじまった。クリストフは指揮をしながら、聴衆の完全な無関心を感じとっていた。次に交響曲が演奏された。この曲に対しても聴衆は無感覚で、プログラムに読み耽けっていた。彼は終わりまでつづけるのが苦しく、いくたびとなく、指揮棒を投げ捨てて逃げ出したくなった。曲が終わり丁重な拍手が起こった。拍手がやんだときに、三つか四つの、ばらばらの拍手が起こった。だが、いかなる反響も呼び起こさなかった。そのため、空虚がいっそう空虚に感じられた。この出来事のおかげで、聴衆は、自分たちがいかに退屈していたかをかすかに理解した。 歌曲がはじまった。聴衆は独唱者を待っていた。彼女は前日クリストフが与えた注意を無視して自己流に歌いはじめた。伴奏していたクリストフは怒り、ついに途中でピアノをやめた。彼は氷のように冷たい調子で言った。「やり直そう!」彼女は彼の威厳ある態度に圧倒され、初めから歌い直した。彼女が歌い終わると、聴衆は熱狂して呼び戻した。彼らが拍手しているのは『歌曲』ではなく、この有名な歌手に対してであった。聴衆はアンコールを求めたが、クリストフはきっぱりとピアノのふたをしめてしまった。 最後の曲はクリストフのオーケストラの同僚であるオックスの『祝典序曲』だった。この平凡な音楽で気持ちのくつろいだ聴衆は、クリストフを非難する意味で、盛んにオックスに拍手喝采を送った。彼は二、三度舞台に呼び戻された。そしてこれが音楽会の最後だった。 新聞の批評では、歌手の技量をほめ、『歌曲』のことは、ただ参考までに述べるにとどめた。クリストフの他の作品については、どの新聞もやっと数行それも似たり寄ったりのことを書いていた。「…対位法には通じている。表現は複雑である。霊感が欠けている。メロディーがない。頭脳で作られていて、心で作られていない。誠実さがない。独創的になろうとしている…」―そして、そのあとに、モーツァルトや、ベートーヴェンや、レーヴェや、シューベルトや、ブラームスなどの《独創的になろうと考えないでしかも独創的である人々》の独創性、つまり真の独創性についての一項が書き添えられてあった。 要するに、クリストフの作品は、もっとも好意ある批評家からは完全に理解されず、彼を愛していない批評家からは陰険な敵意を受けた。最後に、味方の批評家にも敵の批評家にも導かれない大衆のあいだにおいては黙殺された。大衆は、自分自身の考えにまかされると、なにも考えないものである。 2.ロランとクリストフ クリストフのモデルはベートーヴェンだと言われているが、ロランは、この作品の中の、クリストフとベートーヴェンとの伝記的な類似は、第一巻「曙」における、クリストフの家庭のいくつかの特徴だけに限られていると言っている。また、「広場の市」にでてくるクリストフは、若い日のロランそのままである。そして、後に登場するオリヴィエの性格や経験は、ロランのそれと非常によく似ている。このように、ロランは自分自身をこの小説の中の登場人物に投影している。 そこでこの「ぐらつく砂地」での、クリストフのドイツやドイツ音楽についての過激な発言もまた、ロラン自身の考えなのか知りたいと思った。そこで「ぐらつく砂地」を含む『ジャン・クリストフ』の第四巻「反抗」が発表されたのが一九〇六年なので、そのころ発表された他のロランの著作を調べてみると、一九〇八年に音楽評論集『今日の音楽家たち』が刊行されていた。その中に、以下のように、クリストフの発言とほぼ同じ内容の記述があったので、ここでのクリストフのドイツやドイツ音楽についての批評は、執筆当時のロラン自身の考えであることがわかった。 「今日のドイツ人は昔のドイツ人と共通なものはもはやほとんど何ももっていない。 私は単に大衆のことをいっているのではない。今日の大衆は全体として《ブラアムス派》であり、ウァグナア派である。大衆に意見はない。かれには何でもよいものなのだ。ウァグナアに喝采もするし、ブラアムスにもアンコオルを要求する。大衆は、本質においては、軽薄で、センティメンタルであると同時に粗野である。ウァグナア以来、大衆のもっともいちじるしい特色は、力の崇拝である。『マイスタアジンガア』の終末を聴いて、この傲慢な音楽、この帝国的行進がどれほどこの健康と名誉をはらんだ、軍隊的でブルジョア的な国民を反映しているかを感じた しかしもっとも注目すべきことは、ドイツの芸術家がどれほど、日に日に、かれらの偉大な古典派、とくにベエトオヴェンへの理解力を失いつつあるかという点である。」(『今日の音楽家たち』「フランス音楽とドイツ音楽」一九〇五年 野田良之訳) 「ひじょうに教養の豊かなこの芸術家(サン=サアンス)が、いかに自分の学識に煩わされるところが少なく、いかにペダンティスムから自由であるかは注目すべきことである、―このペダンティスムこそドイツ芸術の傷手であり、もっとも偉大な連中もこれから免れられなかった―病膏肓にいたっているブラアムスは言わずもがな、シュウマンのようなもっとも心を魅する天才たちや、バッハのようにもっとも力強い人々においてもまたそうなのだ。」(『今日の音楽家たち』「カミィユ・サン=サアンス」一九〇一年 野田良之訳) 「この世にはブラアムスのように、ほとんど全生涯を通じて、過去の亡霊でしかなかったような人間もいる。」(『今日の音楽家たち』「ベルリオオズ」一九〇四年 野田良之訳) 3.ソフィーアへの手紙 ロランは、『ジャン・クリストフ』のグラチアのモデルとなった、イタリア人、ソフィーア・グェリエーリ=ゴンザーガと一九〇一年から一九三二年の三十一年間文通していた。この膨大な量の手紙の中で、ロランは、心情告白ともいえる人生観や芸術観を語っている。その手紙の中から『ジャン・クリストフ』の第四巻「反抗」に関して書れているものを掲載する。 「『ジャン=クリストフ』の第四巻はまだ出ていません。<カイエ・ド・ラ・キャンゼーヌ>から三冊になって出かかっていますが、それは追ってオランドルフから一巻にまとめて出ることになっています。初めの分冊数巻をあなたにお送りしなかったのは、まず全体をみないうちに作品が批判されることを私はあまり好まないからです。それに、少しあなたのお気にさわるかも知れない心配のあるページを、あまり急いであなたにお目にかけたくないわけです。なぜかというとそれらのページは、あなたが愛するドイツにたいして極度にきびしいからです。私もドイツを愛します、そしてもっと後でドイツの美点をみとめるつもりです。しかし私はまずそのことを言わざるをえなかったのです。それに、クリストフがこうと思いこんだときには、それに反対することは容易ではありません!…それに劣らず激烈な問題を扱ったページがあります。それはユダヤ人について語るところです。現代の社会を描写しようとするときには、今日の芸術と思想において、とりわけドイツとフランスで、じつに重要な役割を演じているユダヤ人を除外することは私には不可能です。私は彼らについて語らなければなりません。そして私はまったく公平に、しかしできるかぎりまったく率直にそれをこころみるでしょう。それはきっと憤慨させるにきまっています。しかし私は平気です。―それに、イスラエル人たちさえも、私が尊敬している多数の人々は、私の言うことは正しいし、私の人物たちは真実だといっています。」(『したしいソフィーア』一九〇六年 宮本正清・山上千枝子訳) |
第224回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年9月28日)
| 第224回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年9月28日) 報告内容 『ジャン・クリストフ』 第三巻 青春 Ⅲ「アーダ」 発表者 清原 章夫 さん 1.あらすじ クリストフは十六才になった。その夏、クリストフと同じ建物の地階に住む二十才の寡婦ザビーネに強く心をひかれ愛するようになる。しかし、彼の愛を伝える前に、彼女ははかなくも流行性感冒で亡くなってしまう。深い悲しみを胸に、ザビーネを思い出すため、彼女の兄が住む農家(ザビーネとクリストフとが、隣り合わせの部屋に泊まった)が見える丘の上へ行くのが、いつもの散歩の目標になる。 しかし、彼は自分の青春にさからうことはできなかった。「生命の樹液は、新たな烈しさをもって彼の衷に昇ってきた。」(以下「 」内 ジャン=クリストフ、片山敏彦訳、みすず書房)彼の内部では、すべてが生を讃えていた。「心の中に死を、肉体のなかに生をもって、悲しさに充ちている彼は、あたらしく蘇る力に―生きることの、夢中な、不条理な歓喜に自分をゆだねた。」こうして、彼は悲しみを乗り越えた。 秋になった。ある日曜の午後、散歩の途中でクリストフは、塀の上に登って李をちぎって食べているブロンドの少女に出会った。彼女の容姿は「彼女の丸顔は、そのまわりに日光の金粉をふりまいているような、ちぢれた金髪にかこまれ、豊かな頬はばら色で、眼は大きくて青く、鼻はいくぶん太く、先が無遠慮に反り返っており、小さな紅い口は白い歯を見せており、強い糸切り歯が突き出ている。食いしん坊の頤。そして彼女の容姿全体が豊麗で、大きくて、肉づきと恰好とがよくできており、しっかりとした作りであった。」といった魅力的な少女であった。 彼女は婦人服店の店員であった。名前はアーデルハイドだが、友達からはアーダと呼ばれていた。彼女は友人達と散歩の途中であったが、友人達とはぐれてしまったのだった。やがて、クリストフとアーダは友人達と宿屋で合流し、一緒に食事をした。友人はクリストフの音楽家としての評判を知っていて、彼に敬意を示した。そのことは、アーダを感激させた。 食後、クリストフとアーダは友達と別に二人で帰りの船に乗るため、船つき場へ行ったが、終発に間に合わなかった。二人は、河岸にある小さな宿屋の部屋で陶酔の一夜をすごしてしまった。「ちらちらとまたたいて光っていた庭の灯が消えた。すっかりの光が消えた…夜…深淵…光もなく、意識もない…《存在》。《存在》の力、幽暗な、そして、むさぼり飲む力。全能の歓喜。おしつぶす力の歓喜。空無が石を吸い寄せるように、生命全体を引き寄せる歓喜。思想をしゃぶる欲望の竜巻。夜の中をころがっていく、陶然たる星々の、不条理な夢中な《法則》…夜…溶けあっている呼吸。溶けあっている二つの肉体の、きんいろの温み。自失の深淵―そのなかに、ともに落下する…かずかずの夜であり、数百年の時間であり、死であるいくつもの瞬時であるような夜…夢を共有し、目をつぶって言葉をいう。なかば眠りのなかでたがいに探しあうはだかの足の、かすかな、そしてひそかな接触。涙と笑い。物たちの空無のなかで愛しあい、まどろみの虚無をともに分け持つことの幸福。」夜が明ける。「彼は目がさめる。アーダの眼が彼を見ている。彼らの腕はからみあっている。彼らの唇がふれる。数分間を、生の全体が通る。―太陽の照る、大きな、静かな日々が通る…《私はどこにいるのだ?そして私は、二人なのか?自分の存在をもう私は感じていない。無限なものが私をつつんでいる。私の魂は、ギリシャの神々のような静かさを湛えた、大きな、澄んだ眼をもつ一つの彫像の魂だ…》彼らはふたたび眠りの数百年のなかに沈む。そして夜明けのなじみ深いいろいろな音―遠くから聞こえて来る鐘、過ぎて行く一そうの小船、水の滴がたれる二つの櫂、路上の足音、それらの音が、彼らの眠たい幸福を乱すことなく愛撫し、彼らが生きていることを彼らに思い出させ、そして生きていることの味を、彼らに味わわせる…」 クリストフは遠足するときにはいつでも、アーダ達といっしょだった。また二人で、劇場や、美術館や、動物園に行った。また、クリストフは、アーダの家を訪ねるのをつねとした。クリストフはアーダを知れば知るほど、アーダが分からなくなった。彼女の関心は、食べること、飲むこと、踊ること、叫ぶこと、笑うこと、眠ることであった。つまり、食いしんぼう、ぶしょう、快楽好きで利己主義だった。また、健康なのに自分の健康についてくよくよと心配し、ばかばかしいほど迷信的だった。さらに、感傷的で、クリストフが許せないほど誠実でなかった。こんな欠点にもかかわらず、クリストフは彼女を愛していた。そして彼女もクリストフを愛していた。「アーダは彼女の愛情においてはクリストフと同じだけ誠実で本気であった。精神的共感に基づいていないからといって、決してこの愛がそれだけ真実でないというわけではなかった。この愛は、低劣な熱情とは無関係であった。それは青春のみごとな愛であった。そして、それははなはだ官能的ではあったが野卑ではなかった。なぜならその愛のなかでは万事が若々しかったから。その愛は、素朴であり、ほとんど貞潔であり、たのしさの熱烈な無意識さに洗われていて純粋であった。」 彼らのことは、隣り近所のみんなが、彼らの出会いの後にすぐに知った。アーダが自慢下に吹聴したからである。小都市では大きな噂になり、宮廷では、クリストフが自尊心を欠いているという非難がわき、中産市民層の人々は、厳格に批判した。彼はいくつかの家庭で音楽を教えることをことわられ、他のいくつかの家庭の母たちは、今後彼が娘に授業するときには、立ち合っていなければならないと思った。特に、フォーゲル一家は、クリストフとローザとの結婚がもう見込みがないと確信していきりたっていた。そして、フォーゲル夫人は、クリストフの母ルイーザに、クリストフの素行について非難した。悲しむ母を見てクリストフは、フォーゲル夫人に抗議し、今後二度とふたたび彼らの敷居はまたがない、と声明した。 その頃アーダは彼女の恋に飽きてきた。「彼女は、クリストフみたいに豊かな性質のなかで、たえず恋ごころを更新してゆくことができるほど十分に聡明ではなかった。彼女の官能と虚栄心とは、この恋のなかから、彼女が見つけることのできるすべてのたのしさを取り出していた。いまではもう後に残っている彼女のたのしみとは、この恋を破り捨てることのたのしみだけだった。」彼女はクリストフの道徳的信念を攻撃した。例えば、「私を愛してる?」「たしかに!」「どれだけ愛しているの?」「愛することができるだけたくさん」「それは、たくさんではないわ…結局!…私のためになにをしてくださる?」「きみののぞむすべてのことを」「そのためなら悪いことでもできる?」もちろんクリストフはできないと答えた。さらに「もし私がほかの人を愛しても、やっぱり私を愛する?」「ああ!それはわからない…きっとそうなったらきみを愛さないだろう…とにかくいずれにせよ、そうなったばあいにきみがぼくに、もう愛さないと告げるよりも先に、ぼくがきみにそう告げることはないだろう」このような議論をアーダは何度も繰り返した。彼は悩んだが、アーダのところを立ち去って十分後には、すべてをけろりと忘れ、再びアーダのところに行きたくなった。彼はアーダを愛していた。 長いこと連絡のなかった末弟のエルンストが、職を無くし、病気になってある日突然、クリストフと母のもとに帰ってきた。しばらくしてエルンストの健康は回復した。ある日曜日クリストフはエルンストを、アーダとアーダの友達ミルハとの郊外遠足に誘った。その時、エルンストがずいぶん前からアーダとミルハの知り合いであったことを知らされ、クリストフは驚いた。その日以後、遠足ごとにエルンストもいっしょに行った。エルンストはミルハに熱中しているらしかった。 彼らは、長い道のりの散歩を何度もともにした。ある日、クリストフが他の三人を残して先に歩いて行ったとき、残りの三人は何かを示し合わせた。次の遠足の際、森の中で道が二筋にわかれていた。クリストフは一方の道をとり、エルンストは、もう一つの道が、丘の頂上への近道だと主張した。彼らはそれぞれの道で競争することにした。アーダはエルンストの意見に賛成したので、アーダとエルンストがいっしょに行くことになり、ミルハはクリストフに同道した。結局、クリストフとミルハが勝った。しかしアーダとエルンストはいつまでたっても来なかった。クリストフはミルハからアーダとエルンストが不倫の行為をしていることを聞かされ、はき出したいほどのいやな気持ちのあまりに、身ぶるいして泣きじゃくった。「アーダはクリストフがまた戻ってくるかと思って二日待った。それから不安になりだして、愛情の言葉を書いたはがきを彼に出したが、それには、こないだの出来事についてはなんにも書いてなかった。クリストフはぜんぜん返事を書かなかった。言い表す言葉も見つからないような深い憎しみを、彼はアーダに感じていた。彼は自分の生活からアーダを抹殺してしまっていた。アーダという存在は、彼にはもうないのだった。」 クリストフはアーダから解放されたが、自分自身から解放されていなかった。彼は過去の力強かった心の落ち着きを取り戻すことができなかった。彼は精神上の危機を通っていた。もうどんな仕事も手につかなかった。そして虚無感から脱するための力も無くしていた。彼は父と同じように酒に酔っぱらうことをおぼえた。 ある晩、彼が居酒屋から出てきたとき、偶然伯父ゴットフリート(神の平安の意)に会う。伯父は彼を見つめて「こんばんは、メルキオールさん」と言った。彼は伯父がもうろくしたと思ったが、ガラス戸に映る自分の姿に、父メルキオールの姿を認め狼狽した。彼はその夜、寝床につかなかった。 翌朝、ゴットフリートはクリストフをメルキオールの墓の前に連れていった。そして祈った後、墓地を出て野道を進んだ。そのときクリストフは泣きだし、自分の恥ずべき点、自分の卑怯さ、心に誓ったことをちっとも実行しなかったことについて話した。ゴットフリートは地平線にさし昇った太陽を指さして言った。「明けてくる新しい日にたいして敬虔な心をおもち!一年のち、十年のちにどうなっているかを考えることはやめるがいい。今日というこの日のことを考えるがいい。理屈はみんな、まずさしおいてしまうがいい。いいかい、みんなだよ。美徳のことを論じる理屈さえもみんなよくないよ。ばかげているよ。悪い結果をもってくるよ。人生に無理な力を加えてはいけないよ。今日を生きることだよ。その日その日にたいして敬虔でおあり。その日その日を愛して尊敬して、なによりもその日その日を凋ませないことだよ。その日その日が花咲くのをじゃましないことだよ。今日みたいな灰いろのくもりの日でも、それでも愛するがいい。くよくよしてはいけないよ。ごらん。いまは冬だ。何もかも眠っている。親切な大地はやがてまた目をさますだろう。自分もまた一つの親切な大地であるがいい。そして大地らしく辛抱づよくあるがいい。敬虔でおあり。辛抱づよく待たなければいけないよ。おまえが善いなら、万事善いだろう。おまえが善くないなら、弱いなら、おまえが成功しないなら―いや、それでもやっぱりそれなりで幸福でなければならないのだ。そのときにはおまえはそれ以上どうにもならない。それならもうそれ以上意志してもしかたがあるまい。できないことのためにくよくよして心をくもらしたって何になるものか。人間は、自分にできるだけのことをしなければならないのだ…Als Ich kann(私にだけのことを)[訳注―画家ヴァン・エックが標語とした句]」伯父と別れたクリストフは、伯父から聴いたばかりの言葉を心にくりかえした「自分にできるだけのことを」そして微笑してこう思った「…そうだ…とにかく…これだけでも十分だ」彼は町に帰った。北風にふかれ凍てついた大地は、ある峻烈な喜びを感じて歓呼しているかのようだった。そしてクリストフの心もまたその大地のようであった。彼はおもった。「ぼくもまた眼をさますだろう」身を切るような寒い風が吹いた「吹け、吹け!…このぼくを、おまえのしたいようにしろ!…ぼくをはこんでいけ!…ぼくがどこに行くかをぼくは知っている」こうしてクリストフの危機は去った。 2.ロランにとっての「存在」と「魂」 クリストフとアーダが過ごした夜の描写で、ロランは『存在』と『法則』と『魂』という言葉を二重括弧で強調している。そこでロランにとってこれらの言葉にどういう意味が込められているかを調べた。『法則』についてはわからなかった。『存在』については、『ロマン=ロラン』(村上嘉隆、村上益子共著、清水書院)にロランのつぎの言葉が引用してあった。「ぼくはもはや『実体』を単に『理性』の一表象として思い浮かべない。それ自体としてそれ自体によってであり、それのうちに全体があり、それによって全体がある『存在』をぼくは感じる。いろんな感覚がぼくをその啓示に導いたのだ。ヴィーナスの前での恍惚、『パルジファル』の前奏曲、『トリスタン』(いずれもワーグナー)それは爆発的な実在感だ…。ぼくは『存在』を次のように定義づける。すなわち、すべて、全体であるもの、全体感覚、全体であり完全無欠であり自由であるという感覚、個別的でない感覚なのだ」と。また『魂』についても同書のなかで、『ロランは、ベートーヴェンの「ゲレルトの宗教歌曲」、「遥かなる恋人によす」などを批評して、「それは音楽ではありません。それは純粋な魂です」といっている』と記述してあった。 3.アーダのモデル ロランがかかわった女性のなかにアーダのモデルになった女性がいたか調べてみた。『ロマン・ロラン』(新庄嘉章著、中公新書)にロランの最初の妻クロティルドに関する次の記述があった。『クロティルドは、ジャクリーヌだけではなく、この作品に登場する他の女性たちにもその影を落としている。たとえば「青年」に出てくるアーダ。彼女は平気で嘘をつく癖があり、また自分の恋人を堕落させて面白がるといったところがあった。もちろんそこには小説的な誇張もあるが、ロランがアーダを描いたときには、きっと眼前にクロティルドの姿がちらついていたにちがいない。』 4.クリストフの名前の意味 クリストフの名前に込められた意味を『ロマン・ロラン―その根本思想―』(蛯原徳夫著、アポロン叢書)より引用する。「ジャン・クリストフ・クラフトのジャンは、ドイツ語のヨーハン(JOHANN)であり、予言者ヨハネを意味する。救世主の到来を告げ、その先駆的な役割を果たす者である。クリストフも人類の救いである生命の更新を告げ、新しい日の先駆者としての使命を生きる。 クリストフとはギリシャ語で「キリストを担ぐ者」すなわちキリスト奉持者を意味し、この名の聖者クリストフォルスは、紀元二五〇年頃デキウス王の治世に、はじめは旅人を肩にのせて川を渡す渡し守であったが、後に篤信なキリスト教徒となり、捕らえられてはげしい迫害に屈せずに殉教したという。伝説によるとある日、幼児のキリストを肩にのせて川を渡ったが、その幼児がしだいに重さを増し、しまいには忍びきれないほどになったが、ついに耐えて対岸へたどりついたとされている。この作品のクリストフにになわされたその聖者伝説の意義は、時代を此岸から彼岸へ渡すこと、つまり宇宙的な生命の展開のはるかな流れのなかで、一つの展開を次の展開へと引き渡すことである。 クラフト(Krafft)は、ドイツ語で力(Kraft)を意味する。この力すなわち生命力によって、人間に先見的にひそむ完成への衝動が、現実の向上意欲となってはたらく。」 |
第222回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年5月25日)
| 第222回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年5月25日) 報告内容 『ジャン・クリストフ』 第三巻 青 春 ─ 第一章 オイラー家 報告者 中 西 明 朗 さん ◇は じ め に 「ジャン・クリストフの序文」から始まり、一回に一章ずつ読み進んできましたこのシリーズも、今回から第三巻「青春」に入ります。 巻のタイトルは片山敏彦訳では「青春」となっていますが、豊島与志雄訳および新庄嘉章訳では「青年」となっています。訳出の順から言えば豊島(1921)、片山(1955)、新庄(1969)となるかと思いますが、どれを優先すべきともいえません。どちらにしてもそれほど大きな意味の違いがないと言えばそれまでですが、何かこれについて訳者のコメントがないか探してみましたが見つかりませんでした。そこで私がかつて慣れ親しんだのが片山訳であったということでもあり、本資料では「青春」としておきます。 さて「青春」最初の章はクリストフが思春期の少年から青春時代へと精神的に脱皮していく過程がテーマですが、その前に生活に疲れてすっかり力を失ってしまった母ルイザのことと、今は亡きジャン・ミッシェルを対比しつつオイラー老人やその家族の様子が語られます。ここで百年後の今、私自身を含め、わが国で多くの高齢を迎えた人々が直面している老年期の問題がいくつか指摘され、すぐれた対処の方法が示されているように思います。 前回私は出来る限り若い人に読んで欲しいと申し上げたことに対して質問と論議がなされましたが、この章をみるとき、決して若い人たちだけに読まれるべき本ではないと言い直さねばなりません。 ◇ あ ら す じ クリストフの父メルキオールが死んで以来、すべてが生気を失い家庭の中は静まりかえっていた。彼はふたたび仕事に没頭してがんばりつづけた。二人の弟は家から出て、ロドルフは伯父テオドールの商会に入り、エルンストはライン川の船の乗組員として雇われていた。今となってはクリストフが生まれ育った家は母と二人で住むには広すぎたし父の借金の支払いも必要となったので、より質素で家賃の安い市場通りの3階にある小さな住居に引っ越すことになった。 引っ越しの準備にかかった母ルイザは、生活のあらゆる思い出がしみこんだ部屋や品々への愛着と、働き続けた疲れから気力をなくしてしまい、ぼんやり坐ったきりいっこうに片づかない。過去の遺物の中に座礁している哀れな魂に、クリストフは心を打たれ母をなぐさめ励まそうと、この日以来母親とできるだけ多くの時間一緒にいるようにつとめた。 引っ越しの当日、どしゃ降りの雨の中、彼らはフィッシャー老人が貸してくれた一台の馬車で、とぼしい家財道具を新しい住まいに運んだ。 夕刻、家主のオイラー老人の誘いで一家の人々の歓迎の集まりによばれた。オイラー老人の娘アマリア、その娘ローザをはじめ皆は、一斉に質問し、よく喋り、議論し、またルイザとクリストフの悲しみをいたわってくれた。二人は疲れきってしまうが孤独の思いは少しは薄らいだ。 オイラー老人は実直で多少潔癖過ぎで、道徳的ではあった。芸術に精通していると自負していたが、実際にはなにも知らなかった。 婿のフォーゲルの方は老人よりも教養があって、芸術界の動きをよく知っていたが、そのためにかえって始末が悪かった、というのは何事にも中傷的な判断と辛辣な皮肉を込めた調子でしか話さなかったから。 フォーゲル夫人(アマリア)は家庭のあらゆる務めを、神聖な義務として熱心に定められた通りに行う働きぶりで虚栄心を満たしていた。だがルイザにたいしてお節介が過ぎるのと、とにかく騒々しいことがクリストフには我慢がならなかった。この騒々しさを憎む気持ちが、クリストフを家の中でいちばん物静かな息子レオンハルトに近づけた。 レオンハルトは聖職者になるつもりだということをクリストフは聞き知っていた。そしてそのことに彼の好奇心は強くひかれていた。クリストフは宗教に対しては奇妙な状態にあった。彼はミサにでかけ、教会でオルガンを弾き信徒としての勤めを果たしてはいたが、神について、イエスについて十分な教育も受けず、また考えを整理することもできていなかったし、自分が神を信じているのか信じていないのか分からず悩んでいた。周囲の人に訊ねても、みな答えは要領を得なかった。またそのことを司祭にうち明けようと試みたが、かえってがっかりさせられた。 そんな矢先、彼は自分と同じ年頃の神を信じている少年レオンハルトを見つけてうれしくなった。彼自身も神を信じたいと思い、レオンハルトを散歩に誘って話を聞くことにした。夕食後、サン・マルタン修道院の回廊で、クリストフはいろいろ質問しレオンハルトもいろいろ語りつづけたが、結局話はかみ合わなかった。レオンハルトはクリストフの精神が、救いがたいほどに病んでいるとあきれ、クリストフは少しも納得できる答えが得られず相手の中に偽善を感じ敵意が募ってきた。 あたりが闇に包まれ鐘の音が響きわたったときクリストフは心の中がすべて変わり、もはや神はなかった、そして信仰が瓦解したことを感じた。 一家の中でクリストフが全然注意を払わなかったのが少女ローザだった。彼女は少しも美しくなかった。クリストフは自分が美しいどころか正反対なのに、他人に対しては、要するに面食いであって美しくない女性は存在しないも同然だった。 ローザにはこれといった長所はなかったが、少なくともクリストフがあんなに愛したミンナよりはすぐれていた。だが彼女はクリストフが逃げ回るほどのおしゃべりだったので、彼の好感は最初の出会いで消えてしまった。数日の間、彼女が親切を尽くそうとしたことが、逆にうるさがられ、三日目にはドアに鍵をかけられてしまった。それでも彼を悪くは思わなかったローザだが、自分ではどうにもならない醜さと、不器用さと、失敗のためにすべてが彼の機嫌を損ねてしまい冷たくあしらわれた。 ある日、ローザが庭のベンチに上り、物干しのロープをほどいて、クリストフの肩につかまってベンチから飛び降りようとしたとき、オイラー老人たちが小声で「似合いの夫婦になるだろうな」と言ったのをちらっと聞いたローザはびっくり仰天し足をくじいてしまった。翌日クリストフはこの禍いがいくらか彼にも責任があると思ったので見舞いにきて、初めてローザにやさしい態度をみせたがその後はもう彼女のことはまったく気にもとめなかった。ローザはクリストフのただの一瞥、一言があればあとは彼女の想像力で際限なくロマンティックな話を組み立てていった。彼女はクリストフの愛を得たい願いをあきらめなかった。そこで彼女はルイザに近づいた。いろんな用事を見つけてルイザに尽くした。ルイザもこの親切でにぎやかな娘がそばにいてくれることはうれしかった。ルイザはクリストフの子供の頃の様子をあれこれと話し、ローザはそれを喜びと感動をもって聞いた。クリストフが夕方帰ってくるとルイザはローザのことをしきりに褒めた。彼は母の顔つきがずっと晴れやかになっているのを感じ、ローザの親切に対して礼を言った。だが彼は彼女のことを思っていなかった。彼はその頃多くのことに心を奪われていた。彼には一つの大きな変化が内部に起こりかけていて、彼の存在の根底までもくつがえされつつあった。 クリストフは極度の疲労と不安を感じていた。頭が重く、耳鳴り、めまいがして、無気力になり、精神の集中ができなかった。夜も昼も彼の内のあらゆるものが動揺し、ばらばらになり、欲望の衝動が彼の中で暴れまわっていた。けだものじみた考えにとらわれ、彼の神も、芸術も、誇りも、道徳的信念も、ことごとく崩れていき、心の中の歯車の装置が狂ったように感じた。 ある晩、自分の部屋で机にひじをついて、ぐったりした麻痺した気持に沈んでいた。虚無が一刻一刻深くなっていき、とつぜん背後の中庭に水門が開かれたように、激しい雨が音をたてて降り出したと思うと、彼の中に幻覚が現れ緊張が走った。閃光に目がくらみ、夜の奥底に彼は神を見た。それは同時に彼の内なる神であった。神が部屋の天井、家の壁を破った。存在の限界を神が取り払った。世界のあらゆるものが滝のように神の中に流れこんで行った。クリストフもまたそこになだれ込み落ちていった。彼は息もつけずにこのなだれ込みに酔っていた。 危機が去ると彼は深い眠りに落ちた。やがて彼は新しい世界を見出した。生き物たちがうごめいている草の中や、昆虫どもがどよめいている木々の蔭に、寝ころがって蟻や蜘蛛やバッタや鎧虫やの動きを見つめた。それまでは彼には理解できない不思議な機械だった虫たちも、今は同じ生命の躍動を満々とたたえて流れる大河のなかの仲間だった。 日々の新しい循環がはじまった。彼は人生を閉じこめる窮屈な規則など笑いとばしていた。 エネルギーに満ちあふれたクリストフは、何もかも壊してしまいたい狂熱的な発作にかられた。 ある夕方、森のはたを散歩していたクリストフは、近くの草はらに肌も露わな姿で、刈り草を乾かしている一人の娘に魅惑された。彼女が近くまで来たとき衝動的に、彼女に飛びつき、抱きしめ、接吻した。彼女は身体をふりほどき、叫び、唾を吐き、彼を罵り、石を投げつけ、逃げていった。クリストフは自分が無意識でした行いが恐ろしく、恥ずかしく、嫌悪感をおぼえた。 彼は家に帰って数日間部屋にこもって外に出なかった。野原に出ると再びあの気狂いじみた風に襲われはしないかと恐れていた。だが彼はその敵がしのびこんでくるには、閉めきった鎧戸に視線が通るだけの僅かな隙間があれば十分だということに気付いていなかった。 ◇興味深く感じられたポイント 1、老後に夫婦の一方が残されたとき心を明るくするためのヒント 「ルイザはメルキオールからいじめられたことはすっかり忘れてしまって、いいことしか覚えていなかった。自分で説明のつかないものは神様にその説明を任せていた」(シ338/ト334) 人生を振り返るとき、愚痴や恨みごとばかりに心が捕らわれるよりも、楽しかったこと、よかったことをたくさん思い出せる方が、心を明るく保ち、落ち込まないで居られるコツであると言っても誤りではないでしょう。性格的なものもありますが、意識的にそうすることは可能だと思うし、心の持ちように関する良いヒントになると思います。 それにしても「他の人から受けた不正当な苦しみの責任は神の手に委ねる」とは、実に巧い言い方・考え方ではないでしょうか。 2、老年期うつ病の危機 「せっせと働き続けた人が、晩年に、なにかの思いがけない打撃を受けて、働く理由をすっかり奪われてしまうと、しばしば神経衰弱(老年期うつ病)の危機に襲われるものであるが、彼女もそうした危機の中にあった。……」(シ338/ト334) そして 「この日以来、彼はこれまでよりも母親と一緒にいるようにつとめた。…母親が孤独に耐えられるほどの力がないことを、彼は感じていた。母親を一人ぽっちにしておくことは危険だった」(シ342/ト338)、1ページで触れましたが、この部分は期せずして現代日本で定年を迎えた以後のかなりの人が直面する大きな問題であります。現に私の身内、知人の中にも何人かいますし、リストラ等で不本意ながら仕事を失った人はなおのことそのような危機に見舞われ易いと思われます。ロランがここでクリストフにさせている対応の仕方は実に適切であります。老年期うつ病は対応を誤ると自殺に結びつくこともあるという点においてロランの言っていることは医学的にも正しい。弱り切った母親の魂をこのように慰められる愛情深い親子の姿、恐らくどんな医療や施設よりも、これにまさるものはないのではないかと思います。 3、内面(心の資源)充実のすすめ 「今では引退している彼は、無為の悲しみをかこっていた。晩年のために内面生活の資源を大切に貯えておかなかった老人たちにとっては、無為であることはつらいことである」(シ349/ト345) また「大部分の人は二十歳か三十歳で死んでしまう。この時期を過ぎると、彼らはもはや自分自身の反映でしかなくなる。彼らの残りの生涯は、自分自身を模倣することに過ごされる。彼らが生存していたときに言ったり、したり、考えたりしたことを、日ごとにいっそう機械的に、またいっそう不細工に繰り返すことに過ごされる」(シ354/ト349)…と。ここでロランは生きるということがどういうことかを問いかけている。そして亡くなった祖父ジャン・ミッシェルは人生を生きていく上にもっとも貴重な特質を持っていた。それはすべてのことに興味を持っていたことであり、寄る年波にも変質されることなく毎朝新しくよみがえってくる新鮮な好奇心であると言う。言いかえれば、精神的に若くあれ、そして興味、好奇心をもって内面(心)の資源を貯えておきなさいと言うことだと思います。確かに老人ホームなどに行きますと、周囲に一切関心を示さず、ただボーっと無為のまま坐ったきりの老人たちばかり、誰が見ても、もはや人生を生きているとは言い難い。ロランはたとえ二十歳代であっても、興味、好奇心を失った人間はそれと同じであると言っているのでしょう、至極もっともなことであると思います。 4、カトリックへの信仰の瓦解と、スピノザ的神への開眼 ①「そして鐘の音の力強い呟きが静まって余韻のふるえが空中に消えたときクリストフは我に返った。彼はびっくりしてまわりを見まわした……もはや何も見覚えがなかった。すべてが変わっていた。もはや神もなかった 、…信仰(に目覚める)と同じように信仰の喪失もまた聖寵の一撃であり突然の光明であることが多い……突如すべてが崩壊する…もはやなにも信じない」(シ369/ト364) ②「ある晩自分の部屋で机の上にひじをついて……閃光に目がくらみ、夜の奥底に彼は神を見た。と同時に神が彼の内にいた。……世界のあらゆるものが滝のように神の中になだれ込んだ。クリストフもまたそこになだれ込み落ちていった。……」(シ390/ト385) この二つの部分の記述はロラン自身の神と信仰に関する体験および思想と深くかかわっている。 先ず①については「ユニテ」29号のD・シッシュ氏の講演記録にもあるように、ロランが青年時代の内心の重要な体験を述べている「内面の旅路」の中で「私が青春の時期に行った第一の行為は自分の宗教(カトリック)と手を切ることであった。…私は見せかけをしたくなかった。信じている風をよそおい、外観だけをとりつくろい、日常の信者の勤めを続けることに耐えられなかった。私は神とのかかわりを嘘いつわりのないものにしたいのです。血を流しているあなたの殉難の像の前に魂の抜けた肉体を跪かせ、心のこもらぬ祈りを口先だけで称えるようなミサにはもう参りません。私はもうあなたを信じていません」それに対して神は「信じないことも、やはり信じることなのだ!」と逆説的に答える。このことがそのまま①の個所に書き表されています。 ではカトリックの信仰を捨てたロランはどんな神を見出したのかと言うと、②の部分が重要なポイントになっています。同じ「内面の旅路」の中に〔三つの閃光〕と題する章があります。三つの閃光とは、ⅰ,フェルネのテラス、 ⅱ,スピノザ(*1)の燃える言葉、 ⅲ,トンネルの暗闇の中でのトルストイ的な閃光、であると書いています。片山敏彦氏は本書の解説の中で、ロランがこのⅱの〈スピノザの閃光的な啓示〉に初めて出会った時の驚きと歓喜の表現が、ジャン・クリストフのこの個所と非常によく似ていると指摘しています。ロランは、スピノザに出会った結果「なぜ特定の、ある姿形をした、ある一人の、神を信じなければならないのか」という疑問から脱却して、「存在するすべてのものは神の中に存在する(*2)。そして私もまた神の中にある!」という考えに共感し、スピノザ的な神を悟ったのであります。 私はさらにⅲの〈トンネルの中での閃光〉も付け加えたいと思うのです。というのは、②の文中で「神は自分のうちにあったのだ。神は部屋の天井を破り、家の壁を破った。神は存在の限界を打ち壊した。神は空を、宇宙を、虚無を満たした」と言う言葉と、〔三つの閃光〕ⅲの「トンネルの中で汽車の狭い箱に閉じこめられたとき、僕は空気よりももっと流動的に、石の天井や壁をつき抜けて脱出する。僕は到るところに存在する、僕は一切のものだ。神は自分の中にある」「…自分自身を全自然と合一させたまえ…」と言っていることとが、非常によく一致していると思うからです。 ロランはその後一年ほどして、トルストイの(戦争と平和)の中に同じ意味の記述(*3)を見出したので「…トルストイ的な閃光」と名付けたようです。 このようにしてロランはスピノザの汎神論的な神に開眼していくのですが、その体験がほとんどそのままクリストフのこの部分に当てはめられているのであります。 (*1) スピノザについて─ オランダのユダヤ系哲学者(1632-1677) ユダヤ教を批判して破門される。レンズ磨きの貧しい境 遇の中で思索し「エチカ〔倫理学〕」「神学政治論」などを書いた。デカルトの合理主義に立脚しながら、その物心二 元論に反対し、個々の事物を神のさまざまな姿と見、神に対する知的な愛によって、神と合一する《汎神論》を唱えた。 その論理の記述は、公理・定義・定理・証明など、純幾何学的に組み立てられている、彼の思想は死後も長く冷遇され たが、一世紀後になってドイツ哲学に大きな影響を与えた。─ 学研、新世紀百科事典より) (*2) この傍点の言葉はスピノザの「エチカ(倫理学)」の中の定理の一つ (*3) 森と野原の姿が、あたり一面にはっきりと見えていた。そして月光をいっぱいに浴びているこれらの森と野原とを越え て、眼差しは無限の地平の奥に沈んだ。ピエールは夜の大空を見つめた。《これらすべては僕のものだ》と彼は考えた ─《これらすべては僕のうちにある。これらすべてが僕だ!…》 ◇む す び 以上のような点を、今回のオイラー家の章で書き出してみましたが、1~3については、二十歳ごろ私がこの部分を読んだとき、どのように感じたか全く記憶にありません。自分にはまだ関係ないと思ったからでしょうか、今の年齢になって読み返してみて関心を寄せる箇所というか、印象に残る箇所が随分変わったものだと感慨を新たにしました。 4の信仰の瓦解と、閃光に打たれ新しい世界を見出す部分については、一見するとクリストフの青春の扉が開かれるにあたって、不安と悩みにとりつかれ精神的な混乱というより錯乱に陥ったさまが描かれ、少しオーバーな表現ではあるが天才ともなればこんなこともあろうか、という印象で読み過してしまうところです。実のところ今回一読したときこの部分にどんな意図と意義があるのかどう要約したら良いものかと大変迷っておりました。しかし少し調べていくうちに前記のことが分かってきましたので報告させて頂きました。そもそも哲学を習ったことのない私にはスピノザについては名前以外はほとんど知らなかったのでありますが、このようなかたちで知る機会が得られロランの思想との関わりも知ることができて大変良い勉強になりました。 さて本章の最後に一つだけ腑に落ちないことがあります。クリストフがあの閃光によって新しい精神へと飛躍し、世界を再び見出し、自然や生物のすばらしさに目覚めた後、なぜ野原で出会った見知らぬ女性に抱きついたりしたのだろうか、この行為はまったく痴漢以下ではないか。精力に満ちあふれたクリストフは物を壊し、焼き、砕きたいなど暴走しかねない狂熱にかられた、とは書いている。しかしクリストフを愛する読者としては、あの閃光に打たれ、理性的にも倫理的にも数段 ている。しかしクリストフを愛する読者としては、あの閃光に打たれ理性的にも倫理的にも数段高みへ飛躍し、崇高であってほしいクリストフが、こんな行為をしでかすとはいかがなものかと思います。順序が逆ならば分からぬでもないが…、それとも次章以後の物語の伏線なのだろうか、ロランの意図はどこにあるのでしょうか?と疑問符を投げかけて私の報告を終わらせていただきます。 |
第221回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年4月27日)
| 第221回 ロマン・ロラン読書会・例会 (2002年4月27日) 報告内容 『ジャン・クリストフ』 第二巻 朝 ─ 第3章 ミンナ 報告者 中西 明朗 さん ◇あ ら す じ 前章ではクリストフとオットーとの純粋で親密な友情関係が周囲から好奇の目で見られるようになり、父メルキオールからも忠告されたことで天真爛漫な関係は毒されてしまう。やがてオットーが大学に入るために町を去っていったことにより終焉を迎えた。 本章は、こうした時期の少し前、クリストフの家の近くにある広大な庭のある邸宅に、夫を亡くしたケーリッヒ夫人と娘のミンナが引っ越してくるところから始まる。 ある日、クリストフが邸宅の庭を囲っている壁から中をのぞき込んでいるところを夫人とミンナに見つかってしまう。その後、宮廷楽団の演奏会で自作のコンチェルトを弾いているのが同じ少年であることを知った夫人は、彼を自宅のお茶に招待する。クリストフのどぎまぎしたぎこちなさも、夫人の好意的なもてなしとミンナの朗らかな笑いで、次第にうち解けていった。クリストフは請われるままにピアノを弾き、賞賛され、そしてミンナにピアノを教えることになる。 ケーリッヒ夫人は聡明で善良な女性であったので、無知で不器用で礼儀作法をわきまえない野生児のようなクリストフに服装からテーブルマナー言葉遣いなどすべてについて、一つのがさずそれでいて彼を不愉快にさせることもなく上手に指導していく。また歴史の面白いところや詩を読ませたりして文学的な素養を身につけるようにも仕向けた。そして彼を自分の家の子のようにあつかい身の回りの世話までしてやる。そんな母性的な親切に対してクリストフは夫人に淡い恋心を抱くが、そこは賢明な夫人に軽くいなされてしまう。 ミンナは彼に対して最初は完全に無関心であった。ピアノのレッスンで彼をわざと怒らせたり、注意されると口答えしたり文句を言っててこずらせた。ある日ふとしたはずみからクリストフがミンナの手にキスしたことで、互いの相手に対する見方は一変する。二人とも驚き顔を赤らめ平静さを失うが、クリストフが帰った後、ミンナははしゃいだり歌いだしたり母親がいぶかるほど有頂天になる。クリストフは自分の行為で決定的に悪く思われたのではないかと怖れていたが、次第にミンナを愛していたことに気がつく。しばらくの間、気づまりな時期があったが、ついにある雨上がりの庭でお互いの本心をうち明けて初恋の喜びに酔う。恋する二人はいろいろのことに感動し、魅力を感じ、根気よくピアノを弾き、すべての人々に対して憐れみと親切心にあふれているように振る舞ったりする。 やがて二人の関係をケーリッヒ夫人に気付かれてしまう。夫人はミンナに対しクリストフの不格好な服装、粗野な笑い声、田舎臭い訛りその他あらゆる欠点を、非難ではなくさりげなく指摘しただけだったが、ミンナの心を刺した棘は確実に残った。 まもなくミンナと母親は親戚のところへ小旅行することになった。数週間別れている間のクリストフの苦しみは耐えがたいものだった。毎日手紙の来るのを一日千秋の思いで待った。やっと来た一通の手紙に心をおどらせるが、すぐにまた待つことだけで生きていた。とうに帰ってくる日が過ぎて、近所のフィッシャーからおととい帰っているよと聞きつけてミンナのもとへ駆けつけたクリストフは、ミンナの冷淡な無関心な素振りに打ちのめされる。 翌朝訪れたクリストフに対してケーリッヒ夫人は娘との交際を慇懃に断った。なんとか気持ちを分かってもらおうとする彼に身分という一語で決定的な拒否宣告をする。クリストフの最後の抗議の手紙に対しても礼儀正しく冷淡な返事に彼はなすすべもなく万事が終わる。 彼は呆然自失となり絶望の淵をさまよい自殺まで考える。母親のルイザは苦しんでいる息子を慰めてやりたかったがどうしてよいか分からなかった。ただそばにいるだけで逆に彼をいらいらさせるだけだった。 そうしたある夜、酔いつぶれて小川で溺れていた父メルキオールがかつぎこまれて来た。臨終の眠りを見守っているクリストフに父のいろいろの姿が目に浮かんできた。「クリストフ、わしを軽蔑しないでくれ」という父の言葉が聞こえてきた。 そしてクリストフは死という現実にくらべれば、ミンナのことも、彼の誇りも愛も、なんとつまらない取るに足らないものであることか、今少しのところで自殺の誘惑に負けかかったではないか、死によって自らをさげすむことの苦しみと罪悪に比べたら、彼の悩みも裏切られた苦しさも幼稚な悲しみにすぎないこと、人生とは休戦のない無慈悲なたたかいであり……目に見えない敵と絶えずたたかわねばならないということを彼は悟った。 そして十五才の少年は自分の神の声を聞いた。「行け、行け。決して休むな」「行って死ね!行って苦しめ!人間は幸福になるために生きているのではない。人間はわたしの掟を成就するために生きているのだ。苦しめ。死ね。しかしおまえがならねばならぬ者になれ。つまり一人の人間に」─と。 ◇この章の意義 本章は単純に見れば、前章オットーと共にクリストフの少年期から思春期にかけての成長の一過程を表わす挿話、初恋の物語として、いつの時代どこの国の人間であれ、同じ年頃の少年が恥じらいと、ときめきをもって一度は経験するであろう普遍性のある物語としてこの章が書かれたというふうに見えますが、この章でロランが本当に言いたかったのは、単に初恋の楽しい夢とそれが破れた悲しみという、ありふれた挿話としてでなく、最後の一ページに集約されている「生への休みのないたたかい」に若者達が勇気をもって挑むよう鼓舞することであったのだろうと私は思います。 一つの比喩をあげるならば、ヨーロッパの代表的な悲恋物語である「ロミオとジュリエット」と一方極めて日本的な近松の浄瑠璃「曾根崎心中」であります。どちらも結末は愛し合う二人の死であり、観客はそういう結末にいたる社会的な背景や不条理に矛盾と憤懣の思いをかきたてられ、死をえらぶ二人の哀れさに涙するという筋書き(実話でもあるのでしょうが)となっています。しかしそこには洋の東西を問わず、死んであの世で結ばれ幸せになれるという、死を肯定し美化する考え方が根底にあるように思われます。ロランはそういう考え方を真っ向から否定しているわけで、前記のとおり「人生とは休戦のない無慈悲なたたかいであり、…目に見えない敵(つまり自然の破壊的な力や、濁った欲望、堕落させようとする暗い思想など)と絶えずたたかわねばならない」と言い、「自ら命を絶つことは最大のさげすむべき行為、罪悪」だと悟らせるのであります。 死まで思いつめる失恋の苦しみではあるが、父メルキオールの死という冷厳な現実を突きつけることによって、もろもろの人生の悩みなど吹っ飛ばしてしまう。そしてクリストフに「人間の名に値する人間になれ。そのためにたたかいに行け。決して休むな」という啓示を与える。真にあざやかな、これほど若者達に勇気と力を与える言葉が他にあるだろうか。 やはりこれは単なる文学的小説ではないというロランの意志を、この章にもはっきりと見ることができます。私はこの章の意義をこのように捉えるのですがいかがでしょうか。 ◇興味深く感じられたポイント *[以下括弧内のトは豊島訳岩波文庫・シは新庄訳新潮文庫のページを示す] 1、身分、階級について─「ミンナが貴族的な名とフォンという文字に誇りをもちながらドイツのささやかな家庭の主婦らしい魂をもっていた」(トP278・シP281)という部分と、ケーリッヒ夫人がクリストフに決定的な切り札として「…身分が…」「夫人はみなまで言う必要はなかった。それは骨の髄まで通す針だった…」(トP318・ シP322)と書いている部分。現代の日本の我々には西欧の貴族などの身分を表す称号、例えばドイツのフォンとかイギリスのサーのもつ重みは判らない。しかしそういう階級・身分が重大なものであったことは理解しておく必要があります。ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェンが晩年に起こされた裁判で、彼の名がヴァンであってフォンではないと言われた侮辱的屈辱的な一言のために体調を崩し半年も寝込んでしまったという話もおそらく本当だったのでしょう、身分、階級というものは我々が考える以上に重大であったことが伺われます。 2、クリストフがベートーヴェンではないという証し─ミンナの仕事部屋の描写で「棚の上には、しかめっ面をしたベートーヴェン、ベレー帽をかぶったヴァーグナーの小さな胸像が、…書架にはジュール・ヴェルヌ(海底二万哩か?)…部屋の真ん中には髭をはやしたブラームスの胸像…」(トP283・シP286)などとジャン・クリストフの時代設定が1890年ころ以後であることが敢えて判るように書いている。ベートーヴェンと別の時代であることをこのような方法で表現しているのが面白い。と同時に今の私達がよく知っているベートーヴェンやヴァーグナー、ブラームスなどあの特徴ある風貌の胸像が、100年前にも一般家庭の部屋に飾られていたことが読みとれて興味深い。 3、朗読に関する記述─ケーリッヒ夫人がクリストフを教育するために「…晩にみなが一緒になったときを利用して歴史のおもしろいところやドイツや外国の詩を読ませることを考えついた」「ミンナは…さわやかな声で読んでいた。勇者や王のせりふをいうときには声を少し渋くして重々しい口調を出そうとした。ときにはケーリッヒ夫人がみずから本を手にとって読むことがあった。…」(トP276.280/シP279.283)クリストフはその朗読がうまく出来ずに笑われてしまうのだが、このような朗読および暗誦という方法は西欧の教養の高い家庭での重要な教育手段の一つであったようだ。たしかロラン自身もそんな家庭教育を受け非常に長い古代ギリシャの叙事詩を暗誦できたことで先生を驚かせたという。今それがどこに書いてあったか手元に見つからなくて正確にお示しできないのですが…、ともかくテレビやファミコンがあふれる現代日本で家庭における子供の教育に関して考えさせられるものがあるように思いました。 4、気まぐれな親切心と内と外での顔の相違─「実を言うと彼らはときどき親切になるにすぎないのだった… (以下本文参照) …彼ら二人の親切は、発作的にあふれ出た愛情の余りにすぎなかった…」実に面白い皮肉っぽい表現ですが、中でも「すべての人間に対する愛に燃え、一匹の虫も踏みつぶさないようによけて通っていたのに、自分の家の者に対してはまるで無関心……冷酷になりさえした」(トP298・シP302)というくだりには、私にもちょっと思い当たるふしがあり、こんなことも世界共通なのかと思わず苦笑してしまいました。内と外で性格態度が全然ちがうのはどちらかといえば日本人男性特有の問題かと思っていましたが、これを読んでひょっとして西欧でも或いはロラン自身もこういう心がどこかにあったのだろうかとも思ってみました。私の周囲や嘗ての職場でも、家庭と職場、仲間内と外に対する場合でまったく別の顔をもつ人をたくさん見てきました。男性と申しましたが例えば病院に入院しますと、これぞ真実の天使か女神かと思えるような、明るくてやさしく頼りになる看護婦さんをいっぱい見かけます。彼女たちが家に帰ってもそのまんま同じならほんとにステキだと思うのですが…。どうなのでしょうか?。 5、母親と息子の親子関係について─ 「ルイザは子供が苦しんでいるのを見た……だが、気の毒な母親は息子と親しく語り合う習慣を失っていた。…で、今息子の力にな ってやろうと思っても、どうしていいかわからなかった。…ただ彼の前にいるというだけのことで、彼をいらいらさせた。…」(トP323・シP326─7) 特に男の子の場合によくあるようですが、ある年齢になると急に親とうちとけた話をしなくなる。テレビドラマでもそんな場面がよく出てきますが、まるで自閉症のようにものを言わない、話を聞こうとしない、話しかけても拒絶的な態度をとるかうるさいと言ってその場から立ち去ってしまう。こういう親子関係もいつの時代、どこの世界にもあったのかと慨嘆をおぼえます。 6、ロランの魂の叫びと考えられる文について ①クリストフの手紙文中─人間を高貴にするものは心です……いかに貴族をもって自任しても、魂の高貴さを持っていない者は、わたしはそれを土くれのように軽蔑します。(トP320・シP324) ②既に前にあげた「人生とは休戦のない無慈悲なたたかい……」の部分。 ③「人間という名にあたいする人間になりたい者」「おまえがならなければならな いもの─、つまり一人の人間に」と言うところの「人間」の意味するもの。 ④神の啓示として「人間は幸福になるために生きているのではない。人間はわたしの〈掟〉(法)を成就するために生きているのだ」と書いています。確か「レ・ミゼラブル」だったか他の映画だったかも知れませんが「神は人間を平等に愛すると言っているのに罪もない幼子や善人の命をどうして無惨に奪ってしまうのですか」と神に愚痴を言う作品があります。おそらくキリスト教の教義でも最も矛盾することの一つではないかと私は思っていたのですが、ロランはこの一言でズバリ愚痴など入る隙のない答を言い当てているのではないかと思います。 以上いくつかの例をあげましたが、ロランがクリストフをして言わしめ、悟らしめ、或いは神の声として彼に語りかけていることは、畢竟、ロラン自身の魂から発せられた叫びに他ならないと思うのであります。 ◇む す び 以上私が偶々気付いたことをいくつか書き並べてみましたが、全体からみれば小さな一章であっても、いろいろなところで、自分にも思い当たること、折にふれて考えていたこと、同じ悩みが書かれていたりして、それに対するロランの思いと心の叫びが聴こえてくる。 そして、実は私もそれが言いたかったのだ!とか、我が意を得たり!と感じさせるところが随所にあって、そのことが共感を呼ぶ所以ではないかと思います。 ともすると近年は以前にくらべて世間のロマン・ロランに対する関心が薄らいでいるように思われます。数多の大学の中でロマン・ロランの講座をもっているところがいくつあるのでしょうか。出版界でもロマン・ロランに関しては戦前および戦後の混乱の未だ治まらない時期に現在よりはるかに多くのすぐれた訳書、研究書、評論が出されていて、よくあの時代にあれだけの本が出版できたものだと感心させられます。それだけすぐれた訳者、研究者、教育者がいてそして多くの読者、ファン、共鳴者がいたからということでしょうか。 どうか本会のような研究会、読書会の輪がさらに大きく拡がっていくこと、特に若い人々、学生の方々が一人でも多くロマン・ロランに関心を寄せ作品を読み共感を得られんことを切に願っております。 |
公開講座 講演会 「ロマン・ロランとトルストイ」

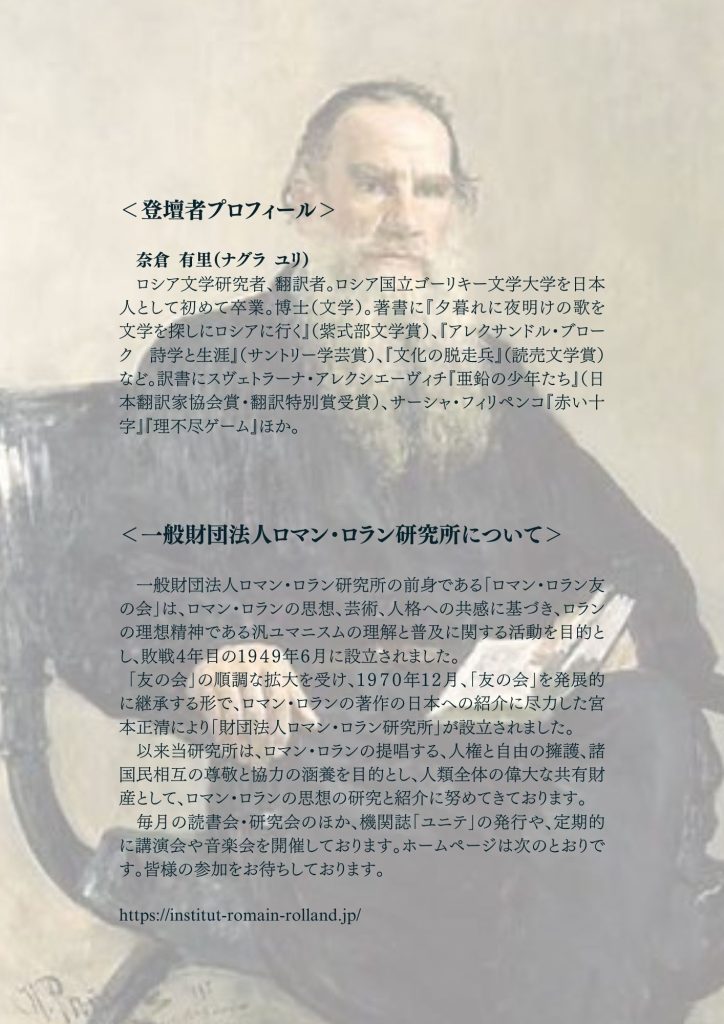
開講座 講演会 「持続する〈ナクバ〉──反復されるホロコースト」
小森謙一郎氏
ナクバとは1948年のイスラエル建国以来、パレスチナの人々が被ってきた苦しみを指す言葉である。演者によると、2023年10月7日に始まったハマスによるイスラエルへの戦闘の前から、ほとんど報道されてこなかったが、イスラエルにより追放、占領、略奪、殺害などが今も続いている。ホロコーストの被害者だったユダヤ人のもとで、なぜアラブ人被害者が生み出され続けるのか、最新の研究に基づいて、ナクバとホロコーストのつながりが解明される。
日 時 2024年5月11日(土)14時~16時(予定) 会 場 アンスティチュ・フランセ関西 稲畑ホール アクセス | Institut français du Japon – Kansai (institutfrancais.jp) 参加費 1,000円 会員、学生無料
講師プロフィール 小森謙一郎氏 武蔵大学人文学部ヨーロッパ文化学科教授。専攻は、ヨーロッパ思想史。
著書に『アーレント 最後の言葉』(講談社選書メチエ、2017年)、『デリダの政治経済学』(御茶の水書房、2004年)、編著に『人文学のレッスン』(共編、水声社、2022年)、訳書にバシール・バシール+アモス・ゴールドバーグ編『ホロコーストとナクバ』(水声社、2023年)、ヨセフ・ハイーム・イェルシャルミ『フロイトのモーセ』(岩波書店、2014年)などがある。
主催 一般財団法人 ロマン・ロラン研究所
『ジャン・クリストフ物語』出版記念 <朗読会とパーティー>
時 2023年10月20日(金)午前11時―午後3時
会場 京都ガーデンパレスホテル
- リコーダ-伴奏による朗読会
出演 リコーダー 村田佳生氏 大阪音楽大学楽理専攻 アムステルダム音楽院リコーダー科卒業
現在 大阪音楽大学 非常勤 講師
朗読者 村田まち子、山本和枝、西尾順子、中田裕子、松田有美子、宮本ヱイ子
(出演順)
第2部 パーティ
着席フレンチ料理
参加費8000円 第一部のみの参加は1000円
お問合せメールはこちら
公開講座 講演会 講師 平野啓一郎氏(作家)
演題 「コロナ共存社会における文学の役割と分人主義」
日時 2023年6月10日(土)14時~16時
会場 京都大学百周年時計台記念館国際交流ホール 定員:80名(先着順) 参加費:無料
平野啓一郎氏プロフィール 1975年愛知県蒲郡市生。北九州市出身。京都大学法学部卒。
1999年在学中に『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。
著書は、小説『葬送』、『滴り落ちる時計たちの波紋』、『決壊』、『ドーン』 『空白を満たしなさい』、『透明な迷宮』、『マチネの終わりに』、『ある男』等 エッセイに『私とは何か 個人」から「分人」へ』、『「生命力」の行方~変わりゆ く世界と分人主義』等。
公開講座 講演会 「生なるコモンズとロマン・ロラン〜文明・戦争・欧州・日韓〜」 濱田陽氏
日 時 2022年11月13日(日)14時~16時 会 場 アンスティチュ・フランセ関西 稲畑ホール アクセス | Institut français du Japon – Kansai (institutfrancais.jp) 入場料 無料
講師プロフィール 濱田 陽(はまだ よう)氏 1968年徳島生まれ、帝京大学文学部教授。京都大学人間・環境学博士。日本文化、比較宗教文化、文明論に取り組み、力強いやわらかさを有する人文学の可能性を切り拓く。
京都大学法学部卒、京都大学大学院人間・環境学研究科文化・地域環境学専攻。マギル大学宗教学部客員研究員、国際日本文化研究センター講師(文明研究プロジェクト担当)等を経て現職。法政大学国際日本学研究所客員所員、賀川豊彦記念松沢資料館客員研究員。
著書に『共存の哲学―複数宗教からの思考形式』(弘文堂)、『日本十二支考―文化の時空を生きる』(中央公論新社)、『生なる死―よみがえる生命と文化の時空』(ぷねうま舎)、『生なるコモンズ―共有可能性の世界』(春秋社)。共著に『現代世界と宗教の課題―宗教間対話と公共哲学』、分担執筆に『環境と文明』『宗教多元主義を学ぶ人のために』『収奪文明から環流文明へ』、『문화로 읽는 십이지신 이야기(文化で読む十二支神物語)』、A New Japan for the Twenty-Frist Centuryほか多数。
主催 一般財団法人 ロマン・ロラン研究所
講演会 『ロマン・ロランと日本の青年』 宮本正清 1971年5月15日
ロマン・ロランと日本の青年(映画『ロマン・ロ
ラン』上映)
宮本
正清
財団法人ロマン・ロラン研究所設立50周年記念 古都・京の記憶に残すべき戦時の日仏交流 ―関西日仏学館― 〈 トークと詩の朗読 〉
ロマン・ロラン セミナー<講演会> ヴイヴェカ―ナンダの生涯とメッセージ 2013年6月22日
公開講演会
インドの賢人 ヴィヴェーカーナンダ生誕150周年記念
「スワーミー・ヴィヴェーカーナンダの生涯とメッセージ」
講師 スワーミー・サッティャローカーナンダ師
場所 アンスティチュ・フランセ関西(関西日仏学館・稲畑ホール)
時 2013年 6月22日 (土) 午後2時―3時半
「ヴィヴェーカーナンダの言葉は偉大な音楽であり、文はベートーベンのスタイル、感動的なリズムはヘンデルのコーラスのマーチのようである。」(ロマン・ロラン)
講師紹介 1949年九州生まれ。1973年神戸大学経済学部卒業。1974年大阪大学、インド哲学科研究生。1976年からラーマクリシュナ教団入門、ブラマチャーリー(修行僧)からインドのハイデラバードの僧院で、世界的に有名なインドの僧スワーミー・ランガナーターナンダ師の下で修行、秘書を経て、現在シンガポール僧院の副院長として霊性の奉仕活動を続けている。
<朗読とピアノ>オマージュ 宮本正清 2013年6月22日(土)午後2時―4時
プログラム & ノート
2013年7月6日(土)午後1時半~3時
会場 アンスティチュ フランセ関西 稲畑ホール
オマージュ 宮本正清 <朗読とピアノ>
<朗読>宮本正清詩集 戦時のつぶやき『焼き殺されたいとし子らへ』
4篇 皺、空、問、わらい *① 宮本ヱイ子
ロラン『戦時の日記』宮本正清 訳 村田まち子
『ジャン・クリストフ物語』宮本正清 翻案
中田裕子 山本和枝 下郡 由 西尾順子
*①わらい コラ ブルニョン …… ロマン・ロランの小説の主人公。ゴール地方の木工職人コラ ブルニョンの飲んで食べて楽しむフランス人特有の自由闊達な物語。
『戦時の日記』
『ジャン・クリストフ物語』
『ジャン・クリストフ』は音楽家の一生を描いた大河小説である。はじまりは幼少期「あけぼの」の巻からである。その「あけぼの」を子ども向けに翻案したものを、今回、音楽を核に主人公クリストフが直面する困難、貧困、差別、いじめ、不正の場面を抜粋して朗読する。
登場人物
ジャン・クリストフ 主人公(音楽家)
メルキオール 父(将来を嘱望されていた音楽家であったが酒におぼれる)
ルイーザ 母(貧しい階層出身)
ゴットフリート 母の弟 叔父 行商人
ジャン・ミシェル 祖父(元宮廷音楽隊長) メルキオールの父
<ピアノ演奏>
・ポール・デュパン/ジャン・クリストフより
「ゴットフリートおじさんとの会話」(8分)
小説中のシーンを忠実に再現した作品。ゴットフリートの素朴な歌は少年クリストフの心に衝撃を与え、その感動は彼の生き方・考え方までにも及ぶ。最後は作曲家デュパンの指示で「大コラールのように」と書かれる通り歌は少年の宇宙に響き渡る。
ドビュッシー/アラベスク 第1番 (4分半)
水の反映 ―「映像 第1集より」 (5分半)
花火 ―「前奏曲集 第2巻より」 (5分)
ロマン・ロランと同時代を生きたドビュッシーの作品から。
「アラベスク」は「アラビア風の唐草模様のように装飾が多く華やかな曲」の意味。
「水の反映」では、水の動きや反射する光の戯れ、またそれを見る人の心の動きまでもが表現される。
「花火」は7月14日・フランス革命記念日に打ち上がる花火や人々のざわめき・興奮が描かれ、最後にはフランス国歌も聴こえる。(岡田真季 記)
Paul Dupin(1865-1949)フランスの作曲家。独学で作曲を学ぶ。ロランの『ジャン・クリストフ』に強い影響を受けて作曲、ロマン・ロランの支援を受け1908年に『ジャン・クリストフ』を発表。孤独と病弱に苦しめられる。
ピアノ 岡田真季
桐朋学園大学音楽学部ピアノ科卒業。パリ国立地方音楽院(現CRR de PARIS)最高等課程で審査員満場一致の最優秀の成績で卒業。東京ニューシテイー管弦楽団、関西フイルとの共演、フランス クレ・ドール コンクール一位をはじめ、国内外のコンクールで優秀な成績をおさめる。2010年5年間の留学を終えて帰国。京都、東京にてソロリサイタル、大阪いずみホールではキエフ国立交響楽団とラフマニノフのコンチェルト第三番を共演。雑誌「音楽の友」にて「多様な音色と響きを曲想に沿って積み上げ、スケールの大きい全体像を構築する演奏家、高い技術と深い音楽性とが相乗した刺激的な演奏会」と評される。
(敬称略)
公開講演会 報告 2012年10月20日(土)午後1時半―3時 「ロマン・ロランと賀川豊彦」―戦いを超えて・死線を越えて-(濱田陽氏)
公開講演会
2012年10月20日(土)午後1時半―午後3時
「ロマン・ロランと賀川豊彦」−戦いを超えて・死線を越えて-
講師 濱田 陽氏 帝京大学文学部准教授
場所 アンスティチュ・フランセ関西(関西日仏学館・稲畑ホール)
ロマン・ロランと賀川豊彦とを合わせ鏡のようにして対比させながら、日本とヨーロッパの偉大な精神がそれぞれにいかにして精神の自由と友を求めて響き合っていったのかを解き明かした講演会であった。
現代の日本に生きる弱い私たちにとって、彼らの偉大な思想に依存するのではなく、それを咀嚼したうえで守り伝えていく必要性が説かれた。
【講師紹介】
徳島県生まれ(一九六八年)。京都大学法学部卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。高校時代にロラン作品、学部在学中にロマン・ロラン研究所に出会い、現代日本人がロランに親しむことの意味について思索を深めた。マッギル大学客員研究員、国際日本文化研究センター講師(文明研究プロジェクト担当)等を経て、現在、帝京大学文学部准教授。専攻は比較宗教文化、国際日本研究、文明論。著書『共存の哲学 —複数宗教からの思考形式—』、共著『環境と文明 新しい世紀のための知的創造』、『韓中日文化コードを読む』等多数。
朗読会 2012年7月28日(土)午後2時―4時 『魅せられたる魂』 第二巻 -夏ー
ロマン・ロラン セミナー
<朗読会>報告
時 7月28日(土)午後2時―4時
所 ロマン・ロラン研究所
テクスト『魅せられたる魂』 第二巻 -夏ー
夏は3部構成であるが、今回は第1回目である。引き続き朗読を予定している。
「闘うため、探すためにして、見出すためならず、また譲るためならず」と扉書に導かれながら物語は展開する。
父のない子を生む決心、母性、世間の偏見、破産、貧困、シングルマザーとして生きる闘いと誇り、恋愛、生と死、神、さまざまなテーマを各自が選択して持ち時間10分で朗読。
朗読案内役 宮本ヱイ子
朗読者 山本和枝、下郡 由、中田裕子、権 英子、西尾順子。
戸外は37度を超える酷暑であった。その暑さに負けない重いテーマの朗読ながら参加者にすんなり入っていく心地よさが和室のサロンに清新な風を送った。女性の真摯な生き方への共感であった。時代背景は1900年のパリ万博から第一次世界大戦勃発まで。
朗読者と参加者の自分体験と女主人公アンネットの生き方を和やかに討論。遠く100年を経ても、遠くパリからも、いかに身近に私たちに迫ってくることか。次回に話をつなげていく。
『ロマン・ロラン伝』翻訳・出版記念会(東京会場)-小尾俊人氏へのオマージュを込めて- 2012年3月29日(木)午後6時―8時
『ロマン・ロラン伝』翻訳・出版記念会
―小尾俊人氏へのオマージュを込めて―
日時 2012年3月29日(木)午後6時―8時
場所 日本出版クラブ会館場所
<プログラム>
1.挨拶 主催者 財団法人ロマン・ロラン研究所 理事長 西成勝好
出版社 みすず書房 社長 持谷 寿夫 氏
編集部長 守田省吾 氏
2.ミニコンサート
琴とヴァイオリン合奏
「春の海 」宮城道雄作曲
「夢のあと」 フォーレ作曲
(出演者)
筝曲家 大谷祥子さん(友情出演)
ヴァイオリニスト 白須 今さん
3.立食パーティー 。
朗読会 2012年3月5日(月)午後2時半―4時 「女たちの祭典・ワークショップ 『魅せられたる魂』を朗読する」
ロマン・ロラン セミナー 2012年3月5日(月)2時―4時
―ひな祭りに寄せてー 女たちの祭典
『魅せられたる魂』 ワークショップ
「アンネットとシルヴィ」を朗読。
朗読者 村田まち子(朗読家)、下郡 由、中田裕子、権英子、山本和枝ほか
司会/進行 宮本ヱイ子
初めての参加者は「魅せられたる魂」に描かれたアンネットの生き方に共感し、
現代社会を生きる女性に通じる強さを発見した。
また、読書会メンバーは、朗読を通して「魅せられたる魂」の魅力を再発見した。
「魅せられたる魂」の朗読会は今後も継続予定。
『ロマン・ロラン伝』翻訳・出版記念会(京都会場)-小尾俊人氏へのオマージュを込めて- 2012年1月27日(金)午後4時―6時半
『ロマン・ロラン伝』翻訳・出版記念会』―小尾俊人氏へのオマージュを込めてー
2011年12月27日(金)午後4時―6時半
<プログラム>
第1部
講演1:「『ロマン・ロラン伝』を翻訳し いま、『ジャン・クリストフ』を読み返して」
村上光彦先生(翻訳者)
講演2:「ロマン・ロランとみすず書房と小尾俊人さん」
守田省吾先生(みすず書房編集部長)
第2部
<立食パーティー>
スピーチ:フランス総領事・関西日仏学館館長 P・ジャンヴィエ・カミヤマ氏
場所 関西日仏学館 稲畑ホール & ル・カフェ
京都市左京区吉田泉田町
朗読会 2011年2月19日(土)午後2時半―4時 「トルストイとロマン・ロラン」
朗読会 トルストイ没後100年に思いを馳せて「トルストイとロマン・ロラン」
日時: 2011年2月19日(土)午後2時半―4時
場所: 関西日仏学館 稲畑ホール
テクスト『伯爵様』 ロマン・ロランとトルストイ往復書簡 蛯原徳夫・訳
『トルストイの生涯』(1911) 宮本正清・訳
1.『伯爵様』より
ロランからトルストイへ ・・・安藤知子
トルストイからロランへ ・・・宮本ヱイ子
2.『トルストイの生涯』
「戦争と平和」より ・・・西尾順子
「懺悔と宗教的危機」より ・・・中田裕子
「復活」より ・・・下郡由
「彼の顔は決定的な顔だちとなり」 ・・・村田まち子
「闘いは終わった」より
公開講演会 報告 2011年11月19日(土)午後2時―4時 『フロイトとロラン -災厄の後に、幻想の前で- 』(小森謙一郎氏)
公開講演会 2011年11月19日(土)午後2時―3時半
『フロイトとロラン -災厄の後に、幻想の前で 』
講師 小森謙一郎氏 武蔵大学准教授
場所 京大百周年 時計台記念館・会議室Ⅳ
ロランとフロイトの間で交わされた限られた書簡などを手掛かりに、
ともに20世紀の偉大な思想家である二人の間の希有な友愛関係と
思考の対話をテーマとして、ヨーロッパ思想史の研究者である
小森氏による講演がなされた。
【講師紹介】
1975年、東京都生まれ。
東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。
専攻:ヨーロッパ思想史。
関連する論文:
「留保された未来」(『思想』第1034号)
「自然学の後に来るもの」(『思想』第1049号)
神谷郁代ピアノリサイタル 10月9日(土)午後2時―3時半 京都堀川音楽高校ホール
神谷郁代ピアノリサイタル
10月9日(土)午後2時―3時半 京都堀川音楽高校ホール
このたびのピアノリサイタルには多大のご尽力を賜りまして誠にありがとうございました。感動的な演奏に温かい拍手が送られました。変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。
なお、当日の参加者は298人。座席数300席。
平成22年度京都市幼児・児童・生徒作品展および姉妹都市交歓作品展 京都市美術館 2010年9月29日―10月3日
ロマン・ロラン研究所に所蔵しています57年前のフランスの子供たちの絵28点を、平成22年度京都市幼児・児童・生徒作品展および姉妹都市交歓作品展に特別に出品させていただきました。
会期 2010年9月29日―10月3日 午前9時―午後5時
会場 京都市美術館 本館
ロマン・ロラン セミナー 2010.7.24
2010年7月24日
ロマン・ロラン セミナー
於 関西日仏学館
小林多喜二とロマン・ロラン
反戦争・世界主義の文学を求めて
エヴリン・オドリ(Evelyne Lesigne-Audoly)
はじめに
小林多喜二とロマン・ロラン - その接点は?
0. 『蟹工船』について(自己紹介に代えて)
『蟹工船』について
小説概要
2008年における『蟹工船』
仏語訳『蟹工船』について
1. 小林多喜二とロマン・ロラン - 平和の使徒・国境なき作家
戦乱の世を背景に、厭戦感が広がったヨーロッパ
早い時期から戦争中止を呼びかけたロマン・ロラン
死にいたる弾圧を恐れず、帝国主義戦争に抵抗し平和のために闘った小林多喜二
2. クラルテ運動と文芸雑誌『種蒔く人』
創刊者:小牧近江
フランスの平和主義と日本プロレタリア文学の架け橋
ロマン・ロランとアンリ・バルビュスの思想に傾倒
日本への帰国後、平和主義の為に活動
3. 反戦文学 - 『蟹工船』の場合
4. 反戦文学 - 『戦いを超えて』の場合
むすび
ロマン・ロランと小林多喜二の響き合う声
ロランと多喜二が21世紀に教えてくれる事は?
講演会 「犠牲の宗教への問い―ロマン・ロランの思い出に」 高橋哲哉氏
講演会
| 「犠牲の宗教への問い――ロマン・ロランの思い出に」高橋哲哉氏略歴1956年福島県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。二十世紀西欧哲学を研究し、哲学者として政治・社会・歴史の諸問題を論究。著書 * 『記憶のエチカ――戦争・哲学・アウシュビッツ』(岩波書店 1995年) * 『デリダ――脱構築』(講談社 1998年) * 『戦後責任論』(講談社, 1999年/講談社学術文庫 2005年,ISBN 978-4061597044) * 『靖国問題』(筑摩書房[ちくま新書], 2005年,ISBN 978-4480062321) * 『国家と犠牲』(日本放送出版協会)と き 2009年10月24日(土)14時 ところ 関西日仏学館 http://www.ifjkansai.or.jp/ かいひ 500円(賛助会員無料) |
フー・ツォン ピアノ リサイタル
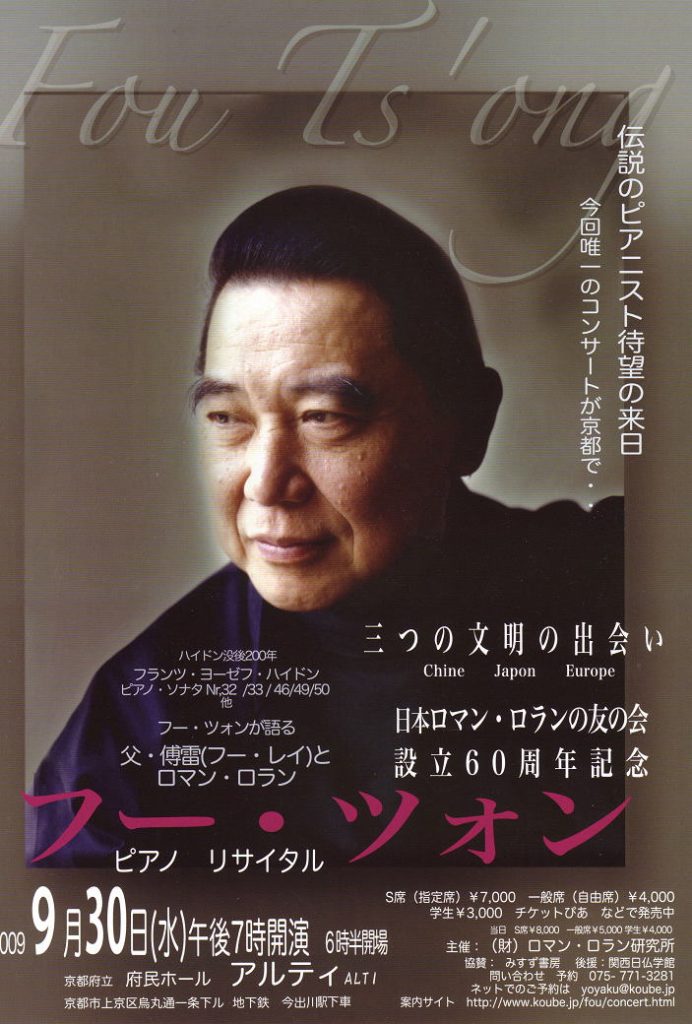

朗読会 『ジャン・クリストフ物語』 生演奏つき
朗読会 『ジャン・クリストフ物語』 生演奏つき
2009年2月7日 於:関西日仏学館
4回目を迎えた朗読会も皆様のお陰様で盛会でした。
今回、初の試みとして、BGMをこれまでの既成のCDから、ピアノの生演奏にしました。
使用した音楽も、ピアノ演奏者の岩坂富美子さんにオリジナル曲を作曲していただき
ました。
朗読と調和がとれていたと、大変好評でした。





ロマン・ロランを偲んで 永田和子
《これは、2008.11.17 高知新聞社 「月曜随想」掲載記事をもとに、編集部で写真を加えて再構成したものです》
ロマン・ロランを偲んで
永田 和子
去る十月二日から五日にかけて第一次大戦終結九十年を記念した国際平和シンポジウムが、フランスのロマン・ロラン協会主催でヴェズ レーやロラン生誕地のクラムシー等で開かれ、わたしたち日本人有志も参加することとなった。

ブルゴーニユにある丘の町ヴエズレーは大河小説「ジャン・クリストフ」で一九一五年度ノーベル文学賞を受賞したフランスの作家ロマン・ロラン(一 八六六ー一九四四年)が晩年の七年間を過ごし、パリ解放まではドイツ軍の監視を受けながら生きていた終焉の地である。
丘の上に建つ聖マリー・マドレーヌ寺院はスペインのサンティアゴ・デ・コンポステラ巡礼の出発点の一つであり、第二次大戦終了の翌年の一九四六年に一人の司祭の呼びかけで「かつて人々が目指した理想の世界を築こう。平和のためにヴェズレーの丘で祈ろう」とヨーロッパ中から四万人の人々がヴェズレーに集まった。

その中に四人のドイツ人が廃材で作った十字架を担って坂道を上っていった。
その十字架は今も寺院の中に飾られている。

研究集会や映画祭などが組まれる中で、京都ロマン・ロラン研究所は聖マリー・マドレーヌ寺院で詩朗読とピアノコンサーを開催した。
詩は戦時中、京都府警中立売署へ連行され、六十一日間の牢獄生活を送った土佐人宮本正清の詩集「焼き殺されたいとし子ら へ」の一節を日仏二カ国語で朗詠し、ピアニスト神谷郁代がべートーヴエンのソナタ「月光」、「ハンマークラヴィア第二楽章」、ピアノ協奏曲「皇帝第二楽章」などを演奏した。特に「皇帝」はナチスドイツの占領直前にベルギーのエリザベート女王がロランを訪問した時、ロラン自身がピアノを弾いて女王を迎えた曲である。

夜九時からはじまった朗読とコンサートは聴衆の心を掴み、閉会後も私たちは語り合い、写真を撮り合って交流し、修道士が「もう入口を占めます」叫ぶまで感動の渦の中に居た。寺院の外に出ると、ヴェズレーの夜空は満天の星が大きく輝いていた。天に近いのだという実感とともに静まりかえつた坂道をわたしたちは坂下の宿の方へ歩いていった。なお午前中にプレーヴの墓参りをすまし、夕方にはクラムシーの町の歓迎会にも出席していた。



翌々日、わたしたちはスイスに向かった。昭和三年、四年と、別々に土佐人の上田秋夫と片山敏彦がスイス・ヴィルヌーヴのヴイラ(荘)オルガににロランを訪ねているからである。

ヴィルヌーヴはバイロンの詩で有名なション城に近く、第一次大戦中、ジュネーヴ国際赤十字の戦時俘虜事務局で働きながら平和活動をしていたロランは大正十一年から十六年間、ヴイルヌーヴで父や妹と住まっていた。上田、片山の泊まったバイロンホテルは門柱二本にそれぞれ「HOTEL」「BYRON」と名前がはめこまれているだけで、はとんど実在しない。ただ一部の建物が老人ホームになっていて、老ヴィクトル・ユゴーが泊まった客間は昔のまま、保存されていた。
「ロマン・ロラン通り」にあるオルガ荘は持ち主が転々としたが健在であった。ロランがその生涯で政治問題に深く関わったのは、このオルガ荘時代である。ロランの話し相手であった胡桃の老樹は今はないが、この庭に来たタゴール一家、ガンジー、ネルー一家、ツヴァイク、マルチネ等、知名人の姿を想像した。ロランが、上田秋夫が片山敏彦が歩んだであろう小径をわたしは歩み続けた。そして眼前にひろがるレマン潮、向こうのスイスの山々の尾根、たなびく白雲、そして風、出発の時を惜しんだ。

(ロマン・ロラン研究所理事
ロマン・ロランと大震災 尾埜善司
ロマン・ロランと大震災 尾埜善司
三年前に阪神大震災がおきました。私たちにとっては突如。ベットの上で激しく上下に何物かにゆすられつつ「死」をイメージしました。廊下をはいながら、ふとロマン・ロラン『魅せられたる魂』の場面が心に浮かびました。シシリア島の大地震でブルーノ・キアレンツア伯は家族と邸宅すべてを失い、心身とも深く傷つきながら沼地の一軒家に一年こもり、雇いの婆さんの熱病をやむ十三歳の息子を引き取り、残った別荘に二人で暮らし、少年を看護し、日々ギリシャ神話を語ってやる。一年後少年は死ぬ。ブルーノは一人で少年をかかえて海の方へ下り、斜面のハタンキョウの若樹の群れに埋め、石の塚を立て唯一の文字を刻む。『不死なる者』――私が大震災直後にイメージしたのは少年を埋めるこの場面です。邸宅の廃墟の上には【光によって、愛を】と記されたキアレンツア家の楯形が残っていました。みすず全集版第三巻185ページ。
それからのブルーノ伯の行動はすごい。インド、チベットにわけいり乞食、巡礼生活も経て危険な社会活動に献身します。
まことにロマン・ロランは大震災を受けた者にも一ページごとに心の安らぎと生き抜くエネルギーを与えてくれるのです。
ロランは心の自伝『周航』で日本に呼びかけています。「神聖な山の下では火が燃え、その火は都市を周期的に揺り動かす。都市たちがその鼓動を感じない日はないが、日本の魂は氷と火と、山と海とで、みずからの調和を作り出している。」
いま私たちはこれに合ったイメージを持っているでしょうか。日本の行政は大震災後、直ちに民家の群れの跡に広い直線道路と画一的なビルの新築のみを計画しました。私たちは、ロマン・ロランが発信してくれているイメージを心にはぐくみ、行動するときに直面しています。 (1998年記)
「ピエールとリュース」の新装版
「ピエールとリュース」の新装版

| ロマン・ロラン 宮本正清 訳 四六判・128頁 みすず書房 定価1680円(本体1600円) ISBN4-622-07223-8 C0097 1965.05.15[初版]2006.05.22[新装] PIERRE ET LUCE by Romain Rolland |
出版 2004年1月 『京 都・半鐘山の鐘よ鳴れ!』 宮本 ヱイ子著
『京都・半鐘山の鐘よ鳴れ!』 宮本 ヱイ子 著
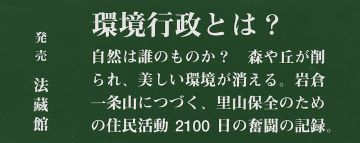

とうとう私はパリまで来てしまった。これまで何度も訪れてきたパリだが、今回は特別の目的がある。ユネスコの世界遺産センターヘ、古都の「小さな山の保全」を要請するためである。京都の市中に残された小さな山だが、私たち住民の暮らしに密着したかけがえのない里山である。破壊は地球環境劣化にもつながる。その思いが昂じて、山の自然を護るため、ユネスコから京都市へ勧告を出してもらう渡仏である。
ユネスコ本部のあるパリは、世界で一番美しい都市と言われている。そのパリには山がない。「山がないから」「人工的な都市だから」と言って、パリを嫌ったフランスの大作家や芸術家のことを私は思い出しながら、京都の山々が与える水を含んだ風を懐かしんでいる。
京都は三方山に囲まれた盆地である。太古の昔、湖の底から形成されたという。京都が醸しだす風景を江戸の文人、頼山陽は「山紫水明の処」と謳い、ペンネームを″東山三十六峰外史”と号した。日本の思想の根元を築いた法然、道元、親鸞、日蓮は、いずれも東山・比叡の山々に籠もり修行した。山には邪気を断ち切る清明な霊気があり、信仰の場であった。
ところが今、京都の存在そのものである山であり、森であるところが危うくなっている。特に京都市街にある法的に守られないヽヽヽヽヽヽヽヽ鎮守の森、子供たちが遊んだ「トトロの山」の原風景である名もない小さなヽヽヽヽヽヽヽ里山に危機が迫っている。
私の住む東山山麓の先端、わが家と隣接する市街化区域に突き出た半島のような小山、通称半鐘山の宅地造成開発問題が起きてはやくも五年が過ぎた。私たちは「半鐘山と北白川を守る会」を結成し、開発反対の運動を展開してきた。京都市が出した「開発許可」に対して、住民側は開発審査会へ、その取り消し請求を提出した。それに対して、「開発は違法ではない」と、二〇〇二年一月二十三日(木)、異例の付言つきではあるが棄却の裁決が出された。現行法では森を守れないことの宣告である。それでは、これらの山林が無秩序に開発され、宅地造成されていく運命として、このまま放置していいものだろうか。
私たちは、京都市長を相手に、二〇〇二年四月二十二日、「開発許可」処分取り消しを、京都地方裁判所へ提訴した。
今、厳しい破壊の現実に直面している半鐘山問題は、京都の市街化区域にある他の三十数カ所、三七ヘクタールの里山や緑地にもあてはまる。そればかりか、日本各地に点在する森、里山、緑地に共通する課題を内包している。しかも、半鐘山は、ユネスコの古都・世界文化遺産に登録されている慈照寺<銀閣寺>の周辺、緩衝地帯バッファーゾ-ンである。そのことを考慮すれば、いっそう放置しがたい重大事件といえよう。
私たちの運動はささやかなものだが、行政、業者、住民が激突した波乱に満ちたものだった。私は住民側当事者として、何はともあれ、この孤独な小山の行く末が気に掛かる。
半鐘山問題の到達点は、今後の環境問題の出発でもあり、判例ともなるだろう。ごまめの歯ぎしりに過ぎない小さな声であるが、私は時を追って書き留めてきた。本書は、台風の日の中にあった、そして今もそこにいる私を通して描く環境ドキュメンタリーである。
「戦い終わって、山無し」では哀しい。しかし、それが、世界中が見ている古都・京都の二十一世紀の幕開けになるかもしれない。
(著書プロローグより、構成:編集室)
下記は、「京都新聞」 2004.01.19 News を引用させていただきました。(編集室)

半鐘山開発の環境運動まとめ
左京 守る会・女性が本出版
東山連峰の銀閣寺山支脈にあたる通称「半鐘山」(京都市左京区)の開発問題で、里山の緑保全を求めて環境運動を続けている住民が、これまでの経過をまとめる本を出版した。突然の開発通告に戸惑った住民たちが、請願や行政訴訟などに取り組んだ経過を市民の率直な感覚でつづり、京都の町と自然のかかわりや環境行政のあり方を問いかけている。
「半鐘山と北白川を守る会」メンバーの同区銀閣寺前町、宮本ヱイ子さん(60)がまとめた「京都・半鐘山の鐘よ鳴れ!」。
半鐘山は銀閣寺山から西へ延びた支脈の先端にあり、市街地に隣接した里山の緑を残していた。ところが、1998年3月に民間業者が宅地開発を通告し、周辺住民らが反対に立ち上がった。最初はなすすべも知らず、市役所のどの課に訴えたらいいかも分からない状況で始められ、本では率直な驚きや憤りを織り交ぜてつづっている。
半鐘山は歴史的風土保存地区などに指定されているが、市街化区域として開発可能地域でもあり、業者の開発申請に対して京都市は許可を出している。現在、住民は市を相手取り開発許可取り消しを求めて提訴する一方、開発工事差し止め仮処分を申し立て、先月、京都地裁が工事を差し止める決定をしている。
こうした運動に加え、里山の緑が京都の町にいかに重要か考えるシンポジウムの開催や世界遺産・銀閣寺の緩衝地帯としての大切さをユネスコに訴えたことなど、さまざまな視点で考えてきた活動を克明に記している。
宮本さんは「半鐘山は市街地と自然の波打ち際。ここが守れないと自然がどうなるか。環境保全に対する法の不備や環境行政を考える教材にと本にした。一石を投じられたらいい」と話す。1800円で法蔵館から全国の書店で発売する。
写真= 「環境行政に一石を投じたい」という「京都・半鐘山の鐘よ鳴れ!」を出版した宮本さん
2003年11月22日 講 演 於京都・関西日仏学館 「ロマン・ロランを読みながら、今の世界を考える」 峯 村 泰 光
ロマン・ロランを読みながら、今の世界を考える
峯村 泰光 みねむら やすてる
ロマン・ロランの一人の読者として、私はいまの時代について、考えていることや感じていることを、おもに戦争と平和の問題を中心にお話ししてみたいと思います。
20世紀には大きな戦争が二度もありました。それはロマン・ロランが生きていた時代のことです。第二次世界大戦の最後にヒロシマとナガサキに原爆が落とされましたが、その前の年の暮にロマン・ロランは亡くなりました。
その後の半世紀あまりにわたる核の時代を私たちは生きてきました。そしていま、21世紀に入ったとたんに、イラク戦争が起こされ、最強国のアメリカによる「新しい戦争」の時代に、おたがい身をさらすことになりました。
そこで20世紀最大の世界市民的なユマニスト、ロマン・ロランを読みながら、この容易ならざる時代を生きのびる手がかりをさぐっていきたいと思うのです。
世界市民についてはあとでまた触れたいと思いますが、ロマン・ロランを読んでこられたみなさんは、すでに世界市民的な感覚を持っておられるのではないでしょうか。ロマン・ロランの大きさを、片山敏彦さんは、ゲーテのようだと言っておられました。また、1966年9月にヴェズレーで開かれたロマン・ロラン生誕百周年記念の国際討論集会で、日本代表として出席した蛯原徳夫さんは次のように述べておられます。
ロマン・ロランは、たんに芸術家であろうとするよりも、みずから真実な人間となることによって、人びとに人間としての本質を意識させようとした。その根本的な影響力は、彼の思想の普遍的性格に由来している。彼は西洋人であるとともに東洋人でもあったのであり、真の意味での「世界市民」(Weltbürger)であった。
と言われて、インドのヴェーダ思想や、ガンジー、タゴールに深い理解を示したロランが、日本の読者にも熱心に読まれている事情を話されました。蛯原さんはまた、『ジャン・クリストフ』の主人公は、「国籍や人種をこえた普遍的人間像、世界市民に成ったのだ」ということも書いています(蛯原徳夫『ロマン・ロラン』アポロン社)。
生きているということ 私がはじめて『ジャン・クリストフ』に出会ったのは、15歳の時でした。そのころ、片山敏彦訳の第一巻〈曙〉が、みすず書房から出たばかりでした。信州の田舎の新制中学で、担任の国語の先生がもっていたんです。
ロマン・ロランの世界は、非常に広くて、深くて、大きいことを私たちはいま知っています。そのことを、その南小川中学校の傳田正直先生は、生徒たちに熱心に話してくれました。あの優雅なフランス装の本『ジャン・クリストフ』第一巻を手に、もう若くはない先生が目をかがやかせて、「生きているということは、素晴らしいことだ」といわれました。私はその本をぜひ読んでみたくなりました。そして貸してもらいました。
この先生はそれまで旧制中学で教えていた人で、歌人でした。宮沢賢治の童話を授業の中でいくつも読んでくれたり、良寛の話をしてくれるような人でした。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を借りて読んだこともあります。私は長野市に生まれて、疎開先の小川村で傳田先生にめぐり逢うことができました。『ジャン・クリストフ』は、まるで太陽のようでした。そして、ここにはなんでも書いてある、と思いました。
その二年後に私は上京して、尾埜さんなんかと同じように、荻窪の片山敏彦先生のお宅に寄せていただくようになりました。ロマン・ロランの友の会の会員で、青木やよひさんにいろいろお世話になっていた一人です。1954年7月末に、第十巻〈新しい日〉が出て『ジャン・クリストフ』が完結した時は、蛯原徳夫先生のお宅で開かれたお祝いの席に参加させていただきました。つまり私は、片山敏彦訳のクリストフとともに成長したということになります。
みすず書房のロマン・ロラン全集が生み出されつつあった頃の東京の様子を、その一端ですがもう少しお話ししたいと思います。
1953年4月下旬に京都と大阪で、片山敏彦、宮本正清、蛯原徳夫の三先生による、ロマン・ロランについての講演会がありました。三先生はそのあと奈良にも行かれましたが、私は、その春から大阪市立大学で教えておられた蛯原徳夫さんと、奈良出身の山口三夫さんのおかげで、それらの催しのすべてに連れていってもらいました。
杉並区沓掛町の蛯原先生留守宅には奥さんが住んでおられました。片山家に近いので、いつのまにか部屋を借りて住みつく人も増えて、私たちは「沓掛御殿」と呼んでいました。そこで毎週のように集まっては賑やかにやっていたのが、村上光彦、清水茂、北沢方邦、美田稔といった、その後ロマン・ロラン全集の訳者に名を連ねる面々です。そのほかにも何人かいましたが、そこに来れば一度に用事の足りる青木やよひさんも時々現れていたと思います。青木さんはその年の2月から東京で開かれていた研究会の世話人でもありました。みんなが集まるのは庭に面した中央の大きな部屋で〈ラルース〉百科事典なんかが並んでいて、そこには山口三夫さんが弟さんと住んでいました。
1954年は中小の出版社がバタバタとつぶれるような不況の年でしたが、『ユニテ』もこの年はガリ版刷りで出ています(Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ)。しかしロマン・ロランの青春の書と、若さの勢いで、あのころの「沓掛御殿」は、本当にいきいきとした祝祭的な気分に溢れていました。「生きているということは、素晴らしい」という感じで、私たちの心にはいつもロマン・ロランが遍在していました。
そしてそのような空気は、そのころ世界と日本の各地に生まれていた「ロマン・ロランの友の会」の活動などもあって、世界中に広がっていたのではないかと思います。当時の『ユニテ』に記録があります。まだみんな貧しかったけれど、戦後の希望に満ちた時代でした。ロマン・ロラン全集について言えば、8年がかりの〈第一次〉が完結に近づいていました。
みすず書房という出版社は、たいへん幸運な出発をしたと思います。推進力の中心だった小尾俊人さんの剛毅な情熱と並はずれた努力は、その魅力的な企画と高雅な装丁造本からも、優れた協力者を獲得していきました。最初の大企画だったロマン・ロラン全集の訳者たちは、さきの三先生はじめみんな、魂の清らかな素晴らしい人たちでした。
私はその後、小さな出版社の仕事や、雑誌の編集も多少経験しましたが、あのように献身的な人たちを見たことがありません。青木さんのような編集者についても同じです。まさに、「ロマン・ロランの友」だったんですね。
ですから私にとって、みすず書房は常に高い峯のような存在でした。15分きざみのテレビ時代になった今では、あのような個人全集や大河小説は、書店の棚では目にすることもできません。そして、版元に一部分少しあるだけで、もう当分は手に入りません。磨きぬかれた〈第三次〉『ロマン・ロラン全集』(以下=全集)を持っている人は、まちがいなく宝の山を持っているのだと思います。図書館にある本もだいじにしたいものです。
「沓掛御殿」の人たちとは、その後も時々会っていました。蛯原さんは15年前、山口さんは7年前に亡くなりましたが、なにしろ、魅せられた魂の人たちですから、いつまでも若々しい青年のような心を持った人たちです。
ロマン・ロランと戦争 さて宝の山の中身のことですが、ロマン・ロランの読まれ方は多様で、それぞれ「私のロマン・ロラン」があるのだと思います。それほどに多面多様な創造的活動を行い、そのいずれもが一等星のきらめきを見せた作家でした。ああいう人はほかにはちょっといないんじゃないでしょうか。いまの時代の物差しに合わないスケールで、時々見えにくくなるのかもしれません。『ユニテ』28号の連載で、村上光彦さんは「わが国におけるロマン・ロラン受容は、いわば蝕の位相にさしかかっている」と言っておられます(蝕は日蝕月蝕の蝕です)。うまい言い方だと思いました。なるほど、いまは曇天つづきで、新しい世代にはなかなか光が届きません。そしてそのことこそが、いまの時代を物語っているのではないでしょうか。
『ジャン・クリストフ』が書きはじめられたのは1903年でした。順次発表されて姿を現したクリストフが、人びとのうちに生きるようになって、今年で100年になります。クリストフの時代背景は、1870年の普仏戦争から第一次世界大戦前夜までですが、主人公はいまなお人びとの心の中に、時代を越えて生きているのです。
ロランは『ジャン・クリストフ』の最終巻〈新しい日〉の中で、世界大戦が始まることを予見しています。それを書いた三カ月後にバルカン戦争が起こり、二年後の1914年には第一次世界大戦が始まりました。空前の大規模な戦争に直面したロランは、たまたま旅行でいたスイスに、腰をおろして、大戦争の本質を見すえることになります。
この時ロランは、スイスの、レマン湖東北岸のヴヴェーに数週間前から滞在していて、まことに幸せな日々を送っていたらしいのです。戦争勃発は「不意打ち」だったと自伝に記し、当時のことを追想しています。
戦争中の私の行動――戦時において戦乱を立ち超えての平和の行動――の反響は世界中にひろがったが、その行動のために、私の内生活の自然な歩みは四年間以上も停止していた。 (全集17巻『内面の旅路』538頁)
50歳の峠を越えながら、ロマン・ロランが心ならずも踏み込んだ、けわしいいばらの道でした。
私はこんどの機会に、ふだんはあまり手をのばさなかった、ロランの『戦時の日記』(全集27~30巻)を全部見てみました。社会評論集(全集18巻)の『戦いを超えて』と『先駆者たち』はこれまでもよく読んでいましたが、〈日記〉といっしょに見ると、第一次世界大戦中のロマン・ロランその人と歴史的背景が立体的に立ち上がってきて、ふしぎな感動を覚えました。『戦時の日記』は単なる日記ではありません。ユニークな記録です。この日記を読み進めると、ロマン・ロランという人の偉大な行動の本質が明らかになってきます。大戦が始まるとどの国の世論も、憎しみの熱に浮かされて目が血走ってきました。ロランはその世論に抗して、ひとり敢然と立ち上がり、堂々と反戦のアピールをヨーロッパと世界に向けて発し続けたのです。
そして、関連する〈書簡集〉も何冊か読むことになり、この読書体験で私は、ロランをいっそう身近に感じるようになりました。ここで個別の内容について触れるのは不可能ですが、印象に残っていることを少し申し上げます。
20世紀は戦争の方法が、科学技術の応用で劇的に変化しました。しかし、第一次世界大戦ではまだ知識人の発言に重みがあり、その代表的存在がロマン・ロランでした。まったくの個人による反戦行動でした。その孤独な闘いぶりと、世間との関係は、戦時に書いて戦後に出版した小説『クレランボー』の主人公に幾分投影されています。そして、その「万人のために、万人に反対する」姿勢こそは、ロランその人の行動原理でした。これは実際には、なかなかできないことだと思います。行動原理にはもう一つ、精神の独立がありました。大戦後、世界の知識人に呼びかけたあの美しい「精神の独立宣言」の基盤になったものです。この二つの原則は、1898年9月の日記に、すでにその原形が誌されています(全集17巻『回想録』264頁)。付け焼刃ではなかったのです。
それにしても、ロランにとっては恐ろしい体験でした。辛酸をなめながら命がけで闘うロランの姿が『戦時の日記』にはあります。スイスにいたので信念を貫くことができたとはいえ、実際に身の危険を覚えることが度々ありました。たとえばそのことを書きながら「憎悪の起源は……〈広場の市〉の時期に発している」と感じることもあります(全集28巻『戦時の日記 Ⅱ』749頁~)。また、パリからやってくる家族と容易に会えない、というようなこともありました。眠れない夜も、多かったようです。良心の自由は、まさに辛酸をなめながら保たれていました。
病気がちのロランにとって、辛酸の味はなじみのものでもありました。1919年10月の日記には『ジャン・クリストフ』を書いている頃の、恐ろしい追想があります。そして、「わたしの医者はジャン・クリストフだった」というのです(全集31巻『インド』537頁)。1913年に初めて対話したツヴァイクも、「どのような精神的な労働力がこの外見のひ弱さの背後にかくれているか……」を後に感嘆をもって認めないわけにはいかなかった、と書いています(シュテファン・ツヴァイク『昨日の世界 Ⅰ』300頁、みすず書房)。
ロランは1914年12月の日記に、ローマ教皇の「回章」の内容を紹介しています。教皇はその中で、社会主義を批難して「富者に逆らう無産の徒は、正義と慈悲とに反して罪を犯している……」などと発言しているのです。ロランはこう書いています。「なんと人をくった慈愛! なんという貴族的な尊大さ! これを書いた人間は決して辛酸を味わったことがないということがわかる」(全集27巻『戦時の日記 Ⅰ』152頁~)。私はこれを読んでハッとし、眼を洗われる思いがしました。
どの国の人々であれ 悩み そしてたたかっており やがて 勝つであろう
自由な魂たちに ささぐ
『ジャン・クリストフ』巻頭のこの言葉は、ロラン自身の辛酸の味から生まれたものだったのです。
しかしクリストフは、戦時にスイスで暮らすロランを、物心両面で大いに助けたのでした。ことに1916年11月にノーベル文学賞を受けたあとは、世界中の熱心な読者からの手紙が、ロランを励ましました。
おもにスイスの新聞に載った『戦いを超えて』の内容は、1915年秋にパリで出版されるまでは、世界に正しく伝わりませんでした。本になると、たちまち各国語に翻訳されて、大戦中の世界に大きな反響を巻き起こしました。
同時に、戦争の煽動者たちによる激しい攻撃の的ともなり、根深い憎悪にさらされます。ところがロランの方は、憎しみを超えていて「私はどの民族も憎むことは出来ない」といいます。ここがロランの偉いところだと思います。
ロランの母の死は、『戦時の日記』の最も痛切な頁です。戦後のパリへ五年ぶりに直行して、母を看取りました。
ヘルマン・ヘッセとの交友は、清らかな美しい物語です(全集39巻)。国際赤十字俘虜事務局で奉仕活動をしていた頃から、ロランは度々ヘッセを訪ね、1922年にヘッセが贈った絵は、妹のマドレーヌ・ロランを魅惑しました。
ロマン・ロランは『マハトマ・ガンジー』(全集14巻)で、ガンジーの非暴力による行動の意味を、第一次大戦後の西洋に伝えました。現代では、人間の普遍的な価値を示す世界の思想として、人類の希望を支えているはずです。
社会評論集の全集18巻は、とてもなつかしい本です。若いころ山口三夫さんたちと時々読みました。『闘争の15年』の中の「過去への訣別」には、第一次世界大戦中のロランの思索と行動が総括的にまとめられています。同じ本の「パノラマ」がそれに続く年月を回顧したもので、この二篇を読めばロランの〈戦争と平和〉論がほぼ概観できます。
『革命によって平和を』は、ヒトラー政権が出現する前後の文章が多いのですが、迫ってくる戦争とファシズムの脅威に対して、ロランが鳴らした「集合太鼓」です。ロマン・ロランは、国際反戦会議のシンボルでした。
ロランは1932年6月に、日ごろ心の底を打ち明けているソフィーアへの手紙でこう言います。
行動は創造と同様に、私が呼吸するときと同様に、一つの自然の要求です。そして私は人類の未来のために闘いつづけますが、人類は結局、希望よりも憐憫の念を私にあたえます。それは自然の非論理性です。(全集35巻『したしいソフィーア』650頁)
ロマン・ロランの精神的自伝『内面の旅路』の中の「周航」は、はじめ1924年に書かれましたが、第二次世界大戦が始まって一年たった1940年9月に、加筆修正されています。
ヴェズレーの家のテラスから、ナチスの軍隊が進撃するのを見ながらも、74歳のロランはこう書いています。
私の全生涯は外観においては敗戦の連続であった。しかし私の内面にいるコラとクリストフとが私に言う――結局のところでは、勝利はわれわれのものだ! ――勝利は私のものである。〔……〕私が欲するのは、人類をみちびいている諸法則が勝つことなのだ。 (全集17巻『内面の旅路』564頁)
ロランはさらに、「私は、戦争のさなかに平和な心をもち、こんな地球の動乱の中で、確かめられた精神をもって、彼らに別れをつげる」と書きます(同、565頁)。そして「宇宙的・普遍的な夢のふところに還り」、「私の畠にもどる」(同頁)ことにしたロランは、『ロベスピエール』、「ベートーヴェン研究」の連作、『ペギー』を仕上げます。1944年夏のパリ解放を見とどけて、年末に亡くなりました。ロマン・ロランは勝っていたのです。
大戦下のフランスでロランは、絶望にさいなまれ、深い悲しみを心の底に湛えていたと思います。しかしロマン・ロランという人は、なんというやさしい言葉を人びとにかけ続けたことでしょう。私はそのことに深く打たれます。
ロマン・ロランが亡くなった半年後にアメリカで原子爆弾が完成しました。最初の核実験が1945年7月16日、ニューメキシコ州のアラモゴードで行われ、その20日後に原爆は、広島と長崎の、人間の頭上に落とされました。
消えた幻影 平和を取り戻した戦後の世界では、ロマン・ロランが盛んに読まれました。戦争から解放された明るい空気の一方で、米ソ対立による東西冷戦の時代が始まっていました。ロランの読まれ方もさまざまだったと思います。それが40年余りしてソ連があっけなく消滅してしまうと、おそらく世界中でロマン・ロランの読まれ方にかなりの異変が起きたものと思われます。その理由のほとんどは、つまりロランの「ソ連擁護」に対する批判ということのようです。そしてそれは、人びとの長年にわたる過剰な思い過ごしだったのかもしれません。
村上光彦氏は、最近の文章のなかで、ベルナール・デュシャトレ氏の『あるがままのロマン・ロラン』から、第二次世界大戦勃発前後のロランの未発表の日記を引用しています。
「わたしとしては、もう憤慨する力もない。わたしには人々が、諸国家が見える。いたるところ、同じである。昔からずっとそうであったように、同じである。彼らの政治は、奸策、野蛮、破廉恥のどれをとっても、なんの新味も見せてはいない。これまでの数世紀にわたってずっと行われてきたとおりの政治である。〔……〕正義と人間性という一新した基礎に立つ新世界がソ連で建設されてゆくものと期待してしまったのが、われわれの誤謬であった。われわれはレーニンの事業を信頼した。だが彼の後継者どもは、いまそれを踏みにじった」。
(つぎに、デュシャトレ氏の文章の要約が続いています。)
彼は、ソ連が〈国際革命〉の名のもとに汎スラヴ的帝国主義の相貌を露骨に示したことも告発した。ソ連は他国を征服しては、それを〈革命〉の美名で飾っていた。ロランはソ連の欺瞞を直視して胸を悪くするのだった。
ロランはそれより先、友人だったゴリキーの死が当局による毒殺だったらしいということに感づいていた。モスクワ裁判が続いて、スターリンがかつての僚友を粛清してゆく様子も遠くからみていた。あれやこれやで彼のソ連への信頼は前から揺らいでいたのだが、いまや最後の幻影まで崩れ去っていった。
そのころ、ロラン夫人のマリーと前夫とのあいだにできた息子のセルゲーがヴェズレーに来ていた。だが、彼はソ連に帰らなくてはならなかった。息子はまずパリに向かい、それっきり音信不通となった(二年後に戦死したことが、後年わかった)。マリーは不安に胸をさいなまれていた。そういう不安の虜となった妻のそばにいて、ロランはソ連との絶縁を公表するわけにいかなかった。彼の発言しだいでは、ソ連に帰ったセルゲーやその家族にどういう危害が及ぶか測りがたかったからだ。彼は(1939年9月末の日記に)こう書きつけた。
「もしわたしに妻がいなかったら(そしてわたしは当人にそう言った)――そしてとりわけ、愛する義理の息子がいなかったら(彼はモスクワで人質になっている)――またわたしがスイスに居住していたら(結婚しなかったらスイスに留まったはずなのだが)、わたしはきっと新しい『戦いを超えて』を書いたであろうに。それは最初のものよりずっと力強く、またずっと報復的なものとなったろう。それが出ると、わたしめがけて、前のよりさらにいっそう憤怒に満ちた憎悪が旋風のように吹きつけてきたろう。――両側からである――わたしはすべてを語り、すべてを告発したであろう。ソ連政府のおぞましい裏切りと、その恥ずべくも非人間的な冷笑的態度とを、――さらにまた英国およびその衛星国たるフランスの金権政府の背信行為を。この両国は不実にも何年も前から、ファシズムともナチズムともいかがわしい駆け引きを演じてきた。〔……〕 しかし、交戦国から発言するのは不可能である。そこでは思考も運動も封鎖されてしまっているから」。
(村上光彦「独ソ不可侵条約調印前後」―『大地』27号所収、大地の会発行)
私はこれには驚きました。ヒトラーやムッソリーニらによる戦争が、ついに始まってしまった時の、ロランの絶望の深さ、その歎きの大きさが噴き出しているとはいえ、こんなに取り乱した感じのロランを日記に見るのは初めてです。戦争を防ぐ力として期待していたソ連政府の裏切りに対する、激しい怒りが鮮やかに書きつけられているので、あえて長く引用させていただきました。それにしても、『新しい、戦いを超えて』をぜひ読みたかったですね。
ロマン・ロランはやはり利用されたのだと思います。党派性や宗派性から常に自由であろうとしたロランは、後半生いつも(たとえそれが善意であるにせよ)利用しようとする人たちに取り囲まれていたようです。しかし1940年9月、『内面の旅路』に、「私は《行動》の圏の外に出ている」と書き加えました(全集17巻、563頁)。
晩年のロマン・ロランの日記は、いずれ21世紀の人びとの前に全貌を現すことでしょう。そこには二つの世界大戦の時代を生きたロランの受難と闘いの人生が、神秘的な、そして極めて人間的な姿で結晶しているものと思います。
デュシャトレ氏の『あるがままのロマン・ロラン』も、早く訳書が出るといいですね。
核の存在 1989年11月9日、突然ベルリンの壁が崩れはじめました。すごいことが起きるもんですね。人間の自然な力の勢いというか、いったん風穴があくと、いわゆる「鉄のカーテン」が次々と取り払われて、すっかり風通しがよくなりました。ひと月も経たないうちにマルタ会談があり、冷戦の時代が終りました。そして東西に分かれていたドイツは、一年後の1990年10月に統一を果たしました。
私はそのころまでやっていたすずさわ書店を退職して、月刊誌の『軍縮問題資料』を手伝うことになりました。そこでまず、ドイツ統一を取材して帰ったばかりのテレビの人に寄稿してもらうことにしました。その人は早速、日独の戦後処理の違いなどもふくめて、歴史的シーンの見聞を書いてくださいました。
これはおもしろいなあと、私は思いました。ジャーナルな感覚で、世界のナマの問題を、ひと呼吸置いて考えていくことができる。それに単行本と違って、短い文章は比較的気軽に引き受けてもらえます。
次の新年号からは、特集方式でいくことになりました。折から人間社会を吹き抜ける新しい風を、テーマ毎にとらえていこうというわけです。当面のいくつかの特集の企画がまとまりました。憲法、国連、中東、それに地球環境や教育の問題などと、それぞれのテーマを中心に、いろいろ工夫して特集を組み、順次原稿を依頼していくというものです。
それまでの出版社の仕事は、ルポルタージュや社会評論などの単行本が中心でしたが、こんどはじかに、正面から世界の戦争と平和の問題に取り組んでいくことになります。そこで友人たちにも声をかけ、ロマン・ロラン全集の訳者や関係者の皆さんにも「賛助出演」してもらうことにしました。表紙裏の〈平和を愛する〉という、すこし面倒なコラムでしたが、大体ずうっと交替で担当していただき、時にはエッセーなども書いてもらいました。
ベルリン統一の三カ月後には、湾岸戦争が始まり、米軍はテレビゲームのような戦況発表をしていました。雑誌は急遽予定を切り替えて、湾岸派兵反対の特集を組みました。こうなるともう、おもしろいなんて言っていられません。私は毎日、戦争や日本の憲法のことを考えていました。この戦争は、冷戦が終わったばかりの時に起こされた戦争ですが、まったく同じ問題をかかえながら今年のイラク戦争につながるものでした。
この1991年は、それからゴルバチョフ大統領が来日したと思ったら、ソ連では夏にクーデター未遂があり、エリツィンが前面に出てきて、年末には突然、ソ連そのものが消えてしまいました。雑誌にとっても慌しい一年でした。
90年代前半は、世界も日本も、まさに激動の時代でした。ソ連が解体して15の共和国となり、新しく生まれたロシアとアメリカの間で戦略兵器削減条約(START Ⅰ・Ⅱ)が調印されました。「第三次世界大戦」はひとまず遠のいたわけです。しかし、旧ユーゴやアフリカでは民族紛争が激しくなり、南北問題はより深刻になりました。
日本でも自民党単独政権から連立の時代に入りました。細川、羽田内閣に続いて、自社さ政権の村山内閣というフシギな時期もありましたが、橋本内閣あたりからしだいに、元のモクアミになってしまいました。
この間私は、特集を作りながら今の世界のことをいろいろと学び、そして考えさせられましたが、六年いて辞めました。1980年に雑誌を創刊した宇都宮徳馬さんは、平和と軍縮を主張する骨太の政治家でしたが、三年前に亡くなりました。「政治は陰謀の世界だ」と言い、核兵器を中心とした軍拡競争を本気で怒っておられました。
核兵器の存在は、私のささやかな市民運動の出発点でした。1965年の春、山口三夫、清水 茂、と私の三人は、幟のような形の手作りのプラカードをかついでベ平連の二回目のデモに行きました。そのころ私たち三人はみんな、人の子の親になったばかりでした。歩きながら渡す私たちのチラシには、「いったん核戦争になれば、地球上に平和で安全な場所はどこにもなくなります。……」などとあります。風が吹くとプラカードが大きすぎて重いんですよね。ベトナムで米軍の北爆(北ベトナム爆撃)が始まって二カ月余り、いま思うと初々しい市民デモでした。生まれたばかりの子供を核戦争にさらすわけにはいかない、というのがその時の私の切実な思いでした。
それからベトナム戦争が終わるまでの十年間、仲間はそれぞれ入り組みましたが、「ベトナム反戦のはがき」67年、「英文・戦場の村」68年、英文“Give Me Water”和文「水ヲ下サイ―広島と長崎の証言」72年、などの、絵ハガキや小冊子を作りました。なんとそのどれもが、みすず書房の二人、青木さんと小尾さんの力をかりています。青木さんは市民の仲間として、小尾さんは陰ながら制作面で、いつも協力してくださいました。
また、新聞の投書欄で知り合った牧師さんたちと、内外の新聞にベトナム反戦の投書などをする運動〈ベトナム反戦市民の声〉というのもやりました。
どれも比較的地味な、世論喚起のための純粋な市民運動でした。戦争当事国のアメリカの市民に直接呼びかける、というのがいつも基本にありました。そして、私のひそかな心のよりどころは常にロマン・ロランでした。
ですから、ロマン・ロラン生誕百年の年に集会を開いて、「ロマン・ロランと現代の会」という読書会を山口三夫さんなんかと始めたのも、行動としての運動とは別の、思想および精神の領域でのことでした。1968年にマリー・ロマン・ロラン夫人が来日されたときには、歓迎会を開いて花束をさし上げました。たのしい会でした。
この読書会の例会は、たぶんこちらの例会と同じようなやりかたではないかと思います。たまには「階級闘争の視点がない」なんていう人もいましたが、『ユニテ』のような記録が残っていないのは残念です。
ベトナムで核兵器は使われませんでした。戦争が終わってから、やはり使う計画があったという記事を二度ほど見ました。朝鮮戦争のときも、マッカーサーが原爆の使用を主張して最高司令官を解任されています。兵器は持っていると必ず使いたくなるらしいです。ですから、反核の運動は多様に重層的に行うべきで、いくらあっても足りない、のだと思います。人間の中の神性が勝つか、悪魔性が勝つか、そのたたかい、または競争なのかもしれません。
新しい人たちがそれぞれに、自分で考えて、核兵器の存在に立ち向かっていってほしいと、私は思うのです。
かすむ平和 冷戦が終って、不戦勝のような格好になったアメリカが、いつのまにか自国中心の、だれも抑えのきかないような国になってきています。それに顔をしかめる国と、おとなしくついていく国があって、それぞれの国の人たちは、さまざまな立場におかれます。正しいか正しくないかより、損か得かが判断の基準に置かれる場合が多く、そのために世界の平和は、かすむ一方で、光が見えません。それはアメリカ人にとっても、本当はいい時代ではないはずです。
21世紀に入ったところで就任したアメリカ大統領は、選挙の前後にいろいろと問題のあったブッシュ二世でした。最初からケチのついたこの大統領は、面目も自信もなくて居直っているうちに、9・11のテロに見舞われ、報復を叫んで一極支配の軍事力を大いに振り回しました。アフガニスタン、イラクと暴れまわり、これからは先制攻撃もやるし、核兵器も使うぞと、世界を脅しています。まるで世紀末のインチキ選挙のツケを、世界中が払わされているようなぐあいで、世界の人びとはまことに憂鬱です。国連も平気で無視するし、国際世論なんて気にもしません。肝心のアメリカ人は、大方が自己中心的個人主義で、世界に無関心だといいます。日本ではいま、エドワード・サイードや、ノーム・チョムスキーの本がよく読まれているようですが、本当にアメリカの民主主義は機能しているのでしょうか。
アメリカの大統領選挙制度については、ロマン・ロランも第一次世界大戦中の日記に「アメリカ人ほどいい加減なものはない」と書いています。新聞に出た当選者ではなく、結果が分らずにいたが、最後にはウィルソンが当選していたというのです(全集29巻『戦時の日記 Ⅲ』983頁)。
あの野蛮な選挙制度は、1787年から引き継がれている成文憲法に縛られていて、改正が困難だというのですが、まずはその憲法を改正すべきだと、国連にでも勧告してもらいたいものです。現代世界の重要課題かもしれません。
核兵器にしても、最大の大量破壊兵器を持っているのはアメリカです。少数の国だけが核保有の特権を独占して、同盟国を傘下に入れながら、小型核兵器を作って実戦に使えるようにしても、解決にはなりません。小型核兵器や生物化学兵器によるテロを最も警戒しなくてはならないのは、アメリカ人自身ではないでしょうか。そして核拡散の流れはもう止めようがないほど激しくなっています。冷戦体制から解放されたロシアは、雪解けどころか、経済危機の大洪水に翻弄されました。核兵器を処分しようにも、その費用さえありません。今でも諸外国の援助に頼っています。失業した核技術者が海外で雇われるケースもあり、核管理の杜撰さは相当なものだといいます。インドとパキスタンは、1998年に核実験をして、核保有国になりました。核拡散を止めるには、核廃絶しかないのです。
核兵器を持つということは、じつに厄介なもののようです。――まず、見えない敵が一度に増える。一気に叩かれて潰されないためには、新たな警戒態勢が必要となる。ミサイル防衛(MD)というような未完成の技術に、莫大な予算を組まなくてはならない(核保有国でもないのに日本はいま、このバカげた計画に参加しようとしていますが…)。持てる者特有の疑心暗鬼も生じる。絶えざる研究・実験や、管理も大変なら、廃棄の費用も積み立てていかなくてはならない。――いいことは少しもないのです。
いわゆる「北朝鮮の核保有」という事態は、日本人にとっては迷惑千万な話です。本来日本は、平和憲法によって自らの「核保有」からも免れているはずです。ところが去年から、「核保有」は憲法違反ではないといっている人がいます。今の自民党幹事長です。アメリカのネオコンに「日本核保有論」を言いたてる人物がいます。焚きつけた者がいるはずです。そういう人たちは、核戦争になったとき、自分たちだけは助かると思っているのでしょうか。
なにしろこの国ではいま、世間知らずの、辛酸の味などまるで知らない三世、二世ばかりの政治屋たちが、相当荒っぽいケンカ腰の外交をくり広げています。国交正常化交渉といいながら、約束は守らないで、ひたすら脅威を煽る。権力の管理下にあるかのように、テレビはこの一年余り、いったいどのような北朝鮮報道をくり返してきたのでしょうか。日本人は冷静さを失ってすっかり変わってしまいました。その勢いに、新聞はほとんどお手上げ状態で同調しています。「北朝鮮の核保有」とは、そのような過程で起きてきた意想外の展開だったのではないでしょうか。
しかし政府の作戦は的中したのです。長年どうにもならなかった有事法制は、なんと九割の議員が賛成して、あっというまに成立してしまいました。イラク派兵法も通り、総選挙後のこれからは、改憲への最短距離をさがして突っ走ろうとするでしょう。北朝鮮の事態は、タカ派の日本政府にまんまと悪用されたのです。今後周辺国は、韓国の意向を益々尊重するでしょう。当然のことです。日本人は、どこで目が覚めるのでしょうか。私は心配しています。
日本人を意識しすぎたので、すこし人間にもどることにします。
世界市民の輪
人間っていい言葉ですね。私は日本人やっていて疲れると、まず人間なんだ、と思うことにしています。
年をとったクリストフがグラチアに会いにローマに行って、そこで国際結婚などによる人間味の豊かな人たちに出会い、古代ローマの奴隷だった喜劇作家、テレンチウスの言葉を思い出します。「私は人間である……」(全集4巻『ジャン・クリストフ』215頁)。
その言葉は、『戦時の日記』の中にも出てきます。 「私は人類に属する。私は人間である。〔……〕私は人間たちの祖国を探し求めている」(全集29巻、1013頁)。スイスにいるロランの悲痛な叫びです。
大戦後にロランは、「戦時の日記」についてツヴァイクに書きます。「この覚え書は個人的価値というよりも集団的証言という関心をひくものです。〔……〕諸国政府やあらゆる国の世論から圧迫され迫害された忠実な『世界市民』たちの証言です」(全集38巻『往復書簡』187頁、1920年1月4日)。ここでの人間は、世界市民に成っています。
現代の人間社会は、自滅の手段を際限もなく作り続け、大殺戮と地球環境の大破壊をくり返しています。人間ほど恐ろしいものはないけれど、ロランのような人のことを思うと、希望や勇気が湧いてきます。ロランは言いました。
人類はなんとただ一つであることか、そしてなんと 相違の少ないことか! (全集17巻『内面の旅路』557頁)。
ロランはいつも、人間の「ユニテ」(調和的一致)のことを考えていたのだと思います。自立した一人ひとりの人間が、「ユニテ」をめざすという感覚でつながれば、世界市民の大きな輪ができるはずです。たとえば、「戦争だけは、ダメ!」と思った人たちが、「戦争やめろ!」「NO WAR!」と叫んで街にくり出したのを、私たちは見なかったでしょうか。皆さんの中には、あの「イラク攻撃反対」のデモを、京都で歩いた人が何人かおられるのではないでしょうか。
それにあの、新聞の反戦大広告(朝日、2003年1月29日付!)を、「その調子をやめよ!」とばかり、華々しく打ち上げた人たちと、協力した人たち……。そのとき、私たちはきっと、小さな世界市民だったのです。去年11月には、あの狭いフィレンツェの道に100万人! 今年2月15日は、60カ国で1000万人の反戦デモが世界を一周しました。
それでもイラク戦争は3月20日に始まり、今のあのザマです。この戦争の大義とされた大量破壊兵器は見つかりませんでしたが、戦後はなりふりかまわず強者にへつらうのが今の世界の流行のようです。果してアメリカは勝利者なのでしょうか。地上最強の武力で一方的に攻め込んだあのような侵略戦争が、人間の歴史の上で正当な戦争として認められるとは到底思えません。
私は開戦まで、こんなに世界中の市民が反対しているのだから、いくらなんでもイラク攻撃はできるはずがないと、祈るような気持で毎月反戦デモに出かけました。テレビもよく見ました。NHKニュースは、アメリカのテレビと同じなので、「フランス2」なんかをさがして見ていました。その後に現実のものとなったあの戦争の結果を、反戦の意思表示をした心ある世界市民たちは、まだだれも認めていないのではないでしょうか。
この戦争は、まだ終わっていません。単独行動主義どころか、単なる暴力主義です。その子分になって、いまからノコノコ出て行くというのでは、世界の物笑いのタネになります。ツケもどんと来るでしょう。平和立国の日本が、正義とはほど遠い戦争に一歩近づいているのです。
作家の池澤夏樹さんは、「世界の人々(の言葉)と国際法と国連が、アメリカの武力に負けた」のだと言っています。(池澤夏樹『世界のために涙せよ』光文社、285頁)
私は、インターネットを操る若い人たちの中に、一つの夢をもっています。「世界市民から世界市民へ」という、反戦反核の大きな輪をつくれないでしょうか。日本語・英語・フランス語・アラビア語……などの恒常的なHPができて、世界市民の大きな輪がしだいに地球全体を包むとき、あるいは突然、「ユニテ」が見えてこないでしょうか。
ロマン・ロランなら、現代の世界市民のための「新しい、精神の独立宣言」を書くところでしょう。人類生存のための普遍的原理である、日本国憲法第九条の精神なども取り入れて、人類の未来に光を灯してくれるでしょう。
はじめにお話しした蛯原徳夫さんは、ヴェズレーのロラン生誕百年記念集会での挨拶を、こう締めくくりました。
今日、この地球上で、物質的な利害関係による憎しみが対立し、無意味で悲しむべき殺戮が残酷におこなわれている。われわれはロマン・ロランの精神を受け継ぐ者たちとして、固く手を握り合いながら、真の平和の実現のために働くことを誓い合おうではないか。
当時はベトナム戦争の真最中でした。いま、世界の現実はさらにきびしさを増しています。私たちはお互いに小さな世界市民として、「ユニテ」による永遠の平和をめざして、世界への関心を一層深めていきましょう。そのようなとき、ロマン・ロランはいつも、私たちを温かく見守ってくれているのだと思います。
『ミケランジェロの生涯』(全集14巻『伝記』215頁)の最後に、作者ロランのこういう言葉があります。
偉大な魂は高い山頂のようなものである。風がそれを打ち、雲がそれを隠す。しかしそこでは他のいかなる場所よりも、じゅうぶんにそして強く呼吸することができる。そこの空気は清らかで心の汚れを洗い落とす。〔……〕 そして日々の闘いのために心を強められて、人生の平野にふたたび降りてくることができるであろう。
ロマン・ロランも、とくに見事なそういう山頂だと思います。作品だけではなく、その山ぜんたいの自然や音楽にいたるまで、ロマン・ロランから受け取ったものがどんなに大きいかを思い、ロランに連なる人たちにあらためて感謝しながら、つたない話を終わりたいと思います。
(元すずさわ書店社長)
2003年11月22日、関西日仏学館でのロマン・ロランセミナー講演会から。
